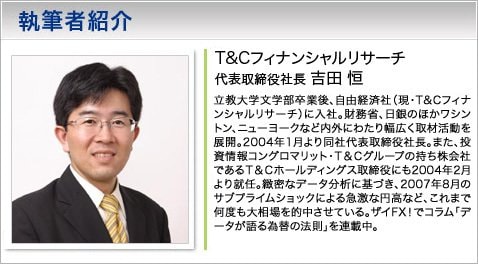
<要点>
・アイルランドが主役を演じる欧州財政危機第2幕は、ギリシャが主役で展開した「第1幕」と多くの点で違いがある。
・「第1幕」は欧州全体の信用悪化と欧州コア国の金利低下により「ユーロ危機」に発展していったが、「第2幕」での「ユーロ危機」再燃は微妙だろう。
・ただし、12月EUサミットへ持ち越しになっているソブリン債務の投資家への強制負担を巡る独仏vs「ユーロの番人」ECB対立の行方は要注意か。
■「欧州危機=ユーロ離れ」第2弾は起こらない!?
10月末から、アイルランドを主役とした欧州財政危機第2幕の様相となってきました。ただこの「第2幕」、今年6月にかけて展開した「第1幕」とはいくつかの点で明らかに違っています。
ギリシャが主役となった欧州財政危機第1幕では、欧州全体の信用悪化からユーロが一本調子で売られるといった「ユーロ危機」へ発展するところとなりましたが、「第2幕」はそれとはちょっと違うのかもしれません。
「第1幕」と「第2幕」の顕著な違いの1つは、金利の動きです。
第1幕では、ギリシャなど財政危機に陥った国から、欧州域内の「安全圏」独への「質への逃避」が広がった結果、両者の金利差が拡大する中で、とくに独金利は短中期中心に大幅な低下となりました。しかし、第2幕では、これまでのところ独金利は高止まりが続いています。
たとえば、1年もの独国債利回りは、今年初めは0.8%程度だったのが、6月にかけて一時0.2%台へ大幅に低下しました。このような独金利の低下がユーロ売りを後押しした面は大きかったと思います。
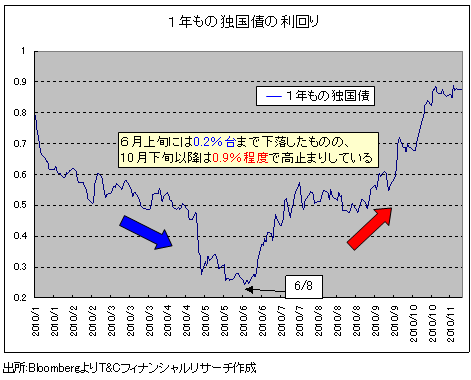
実際に、独金利とユーロの相関性は高く、両者の安値はともに6月初めとなっています。
10月末のEUサミットのあたりから、アイルランドを主役とした欧州財政危機第2幕が始まりました。しかし、その中でも、これまでのところ2年もの独国債利回りは年初の水準よりわずかに高い、0.9%程度での高止まりが続いています。
これは、11月初めのFOMC(米連邦公開市場委員会)、米10月雇用統計発表などをきっかけに米金利が反発に向い、それがリード役になり世界的に金利上昇の動きになる中で、独金利もそれに連動している影響が大きいでしよう。
それにしても、これまでのところは米金利上昇に伴う米ドルの買い戻しが強いわけですが、独金利がこのまま大きく下がらない中でもユーロが大きく売り込まれ、「ユーロ危機第2幕」になるといったことはあるのでしょうか?
欧州財政危機第1幕と今回の第2幕のもう1つの大きな違いは、これまでのところ、欧州全体の信用が大きく悪化する動きにはなっていないということです。
アイルランドやポルトガルなどの一部の国債利回りは急騰していますが、たとえば、欧州全体の信用リスクを示す「欧州CDS指数」は、6月から続いてきた改善傾向から高原横ばいの動きにとどまっています。
アイルランドやポルトガルなどの一部の国債利回りは急騰していますが、たとえば、欧州全体の信用リスクを示す「欧州CDS指数」は、6月から続いてきた改善傾向から高原横ばいの動きにとどまっています。
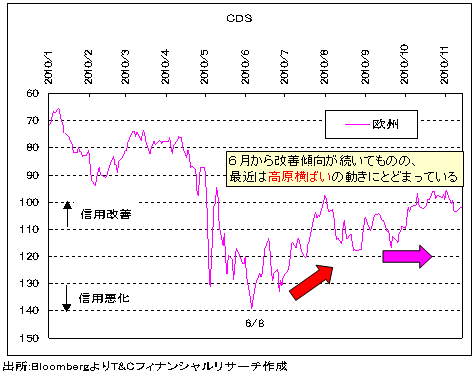
こんなふうに「第1幕」と「第2幕」でかなり違いもある中で、その意味では欧州危機「第2幕」と呼ぶのも微妙かもしれないところが、欧州危機再燃に注目が集まっているのは、ユーロが急落している影響が大きいでしょう。ただ、このユーロ売りも、細かく見ると「第1幕」とは違うようです。
CFTC(米商品先物取引委員会)統計で投機筋のユーロ・ポジションを見ると、昨年12月頃からギリシャをきっかけに欧州財政危機が起こると、投機筋はユーロ売りリスクの拡大に動きました。
「欧州危機=ユーロ離れ」の構図が明確になっていたわけです。
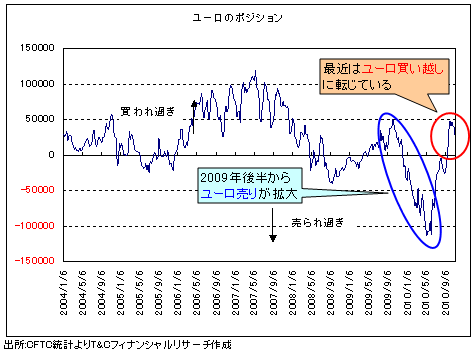
これに対して、最近にかけての投機筋のポジションはユーロのネット・ロング、つまり、買い越しが続いています。この裏側では、米ドルがかなりの「売られ過ぎ」になっていました。
最近の米金利上昇を受けて、そんな米ドル「売られ過ぎ」の修正が広がっているということでしょう。「欧州危機=ユーロ離れ」第2弾が起こっているというのとは違うでしょう。
■それでも気になる「独仏vsECB」の行方=ソブリン債務の投資家負担案
これまで見てきたように、欧州財政危機第1幕と最近の動きはかなり違っていると思います。
それでもまだ先行きに一抹の不安を残しているのは、今回の危機第2幕のきっかけになった10月末のEUサミットにおける財政不安を抱えた国への支援策の議論が、12月に予定されているサミットまで決着を先送りした形になっているということがあります。
そもそもこの中で、独・メルケル首相が金融危機に陥った国への支援について、当該国の国債に投資していた民間投資家にも負担させる提案をしたことが、懸念される国の国債売りにつながったとの見方もあります。
このような独の提案に対して、欧州のもう1つの有力国である仏・サルコジ大統領は、当初は反対との見方が強かったのが、最終的には受け入れた形となりました。
ところが、「ユーロの番人」、ECB(欧州中銀)トリシェ総裁は、この独仏合意に対して、「周辺国の市場に大混乱を招く」として強い懸念を示しています。
このように、「ユーロの番人」が強い懸念を示しているソブリン債務の民間投資家に対する負担強制という独仏合意の取り扱いが12月EUサミットにかけて未決着のまま残っているということは、「第1幕」とは違うものの、欧州危機第2幕の行方をなお予断許せないものとしている可能性はあるのかもしれません。













![トレイダーズ証券[みんなのFX]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C14464&lc=PAN1&isq=130&psq=0)
![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)








株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)