■市場センチメント急変、米ドル全面高は続くのか?
米7月追加利上げの観測が高まりつつある。それにともない、米ドル全面高の市況となっているのは当然の成り行きとみなされる。
しかし、テクニカルの視点では、ドルインデックスの下げが一服するという可能性が強かっただけに、こういった流れに後付けの形で利上げ観測が再燃するのは、サプライズというよりもむしろ、よく見られるパターンの1つだと思われる。
(出所:CQG)
もっとも、こういった市場センチメントの変化は急速に行われ、ドルインデックスの切り返しも急速に行われてきたから、これからの継続性が問われるだろう。
米金融政策に関して、つい最近まで、「6月追加利上げはなし、年内2回」といった見方が主流であったが、先週(5月16日~)にかけて一転して「早ければ6月利上げもあり得る」といった観測が急速に高まってきた。
米経済指標の改善云々より、米連銀理事のタカ派発言が市場センチメントを修正させた原因として挙げられやすいだろう。では、一部FRB幹部の強気スタンスは、どこに根拠があるのだろうか。
■一部FRB幹部の強気スタンスの根拠は?
先週(2016年5月20日)のコラムで既述のように、FRB(米連邦準備制度理事会)は景気云々よりも金融市場の安定やチャイナリスクを懸念していたから、この2つの要素がもっとも大きい。そして、両要素はコインの両面のように、実は同じであることを強調しておきたい。
【参考記事】
●急に高まった6月米利上げ説は正しい?そろそろ米ドル売り・円買いの好機到来か(2016年5月20日、陳満咲杜)
言い換えれば、昨年(2015年)夏場から秋口にかけて発生した世界金融市場の混乱の発端が中国であった以上、チャイナリスクの存在は、これからも撹乱要素として見すごせない。
一方、中国株にしても、中国人民元の動向にしても、不安定な状況が続いているものの、昨年(2015年)のバブル崩壊時の水準に比べると、足元ではかなり低いレベルにあるから、これから続落してもそのインパクトは低下していくに違いない。
ゆえに、チャイナリスクは当面くすぶるが、その影響力は逓減しているから、これが原油や米国株の大幅リバウンドにつながったと言える。
原油と米国株の反騰が、一部FRB幹部の強気につながったとしても別に不思議はないのではないだろうか。言い換えれば、理屈ではいろいろ難しく語れるが、結局、金融市場次第、ということである。
■原油と米国株の上昇はこのまま続くのか?
となると、これから市場センチメントにしても、米ドル全体の値動きにしても、金融市場の動向次第で再度チェンジする可能性が大きい。果たして原油と米国株の上昇は続くだろうか。
(出所:CQG)
テクニカル上の視点はいろいろあるが、上のチャートで読み取れるRSIのサインが正しければ、原油の反騰が行きすぎの領域に入っていることがわかる。
要するに、原油は以前の「売られすぎ」の状態から一転して「買われすぎ」の状態になっているから、近々再度修正される公算が大きい。同じ状況が、目先の米国株にも当てはまる。
(出所:CQG)
NYダウの月足を見る限り、長年構築されてきた大型RSIの弱気ダイバージェンスのサインが有効である限り、米国株が再度大きく反落してもおかしくなく、また、場合によっては2008年のような大暴落につながる可能性がある。
一方、昨年(2015年)8月や今年(2016年)1月の急落では、短期スパンにおける「売られすぎ」のサインが点灯していたから、足元までの反騰は、原油同様に「売られすぎ」に対する修正にすぎない。
ここで注意すべきなのは、6月利上げ、あるいは7月利上げ観測が急速に浮上してきたのに、これが米国株への売り圧力として、あまり鮮明になっていないことだ。
この意味では、米国株の上下は、結局、リスクオン・オフの反映で、利上げ自体がリスクオンと解釈される場合、やはり、これ以前の「売られすぎ」に対する修正、すなわち反騰が維持されるといったコンセンサスにつながりやすいかと思われる。もちろん、こういったセンチメント、長く続くものでないことは言うまでもないが…。
■本格的な米ドル高につながる決定打を欠いている?
となると、一部FRB幹部の強気発言に惑わされず、しっかり市場の状況を見極めるべきであろう。米利上げの可能性が市場次第なら、また急速に修正される恐れがあるので、米国株高にしても米ドル高の継続性にしても、あまり過信しすぎない方がよさそうだ。
とはいえ、利上げ観測が高まってきたものの、その確実性について、市場は疑心暗鬼になっているところがある。いってみれば、米ドル高シナリオは、米国が追加利上げできるかどうかにかかっている。
しかし、4月のFOMC(米連邦公開市場委員会)議事録が公表されて以降、ドルインデックスの切り返しは見られているが、本格的な米ドル高につながるには決定打を欠いているようだ。
理由の1つは経済指標の結果である。
FRB自身が指摘した「第2四半期に経済成長を加速、インフレと雇用環境がさらに改善される」という条件を満たせない可能性が、BNPパリバをはじめとした、ウォール街の投資銀行の一部から指摘されている。どうも懐疑的な見方を示すアナリストが多いようだ。
さらに、FRB内部の意見が一致していないことが指摘される。
実際、タカ派とされる理事が投票権を持っていなかったり、投票権を持つ理事の意見がより慎重になっていることがFRBの声明文を精読すればわかる。言い換えれば、公の談話よりも議事録の内容が大事だということである。
したがって、米ドル全体の切り返しは、しばらく続く可能性が大きいものの、米追加利上げが現実的になるまで、あまり楽観しすぎないほうがよい。
その上、市場次第では、米利上げ観測自体が急速になくなる可能性も小さくないので、リスク要素として要注意だと思う。市況はいかに。

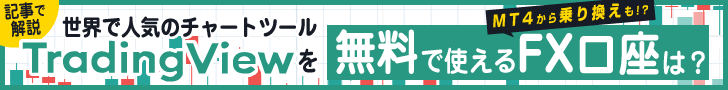















![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)







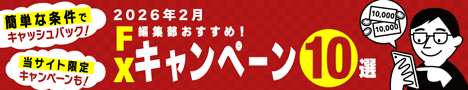
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)