昨日はクリスマス明けだが、欧州のほとんどの国がお休み。米国市場でも相場はほとんど動かなかった。マーケットが動くのも今日と明日だけであろう。
今年の振り返りの第4弾で、株価について見ていく。昨年秋の米大統領選の後、トランプラリーが続いている。今年の多くの日で、終値が歴史的な最高値を更新したというニュースが出たものである。マーケットはトランプ大統領の政権公約を真に受けたわけではないが、それでも何をやるのかわからない怖さもある。
オバマケアの修正やメキシコの壁については早々に断念を余儀なくされたが、今年の終盤になってエルサレムの大使館移転と法人減税が実現化した形となっている。公約を守るリーダーだという面目は保たれたわけである。
ダウ平均もS&P指数も年初のレベルから3割近くも上昇している。この上げ幅は株価指数としてはかなり大きなものである。平均値が3割も上がっているということは、中には下がっている株もあるはずだから、物によっては2倍以上になった株もあるということを意味している。確かに時価総額の上位5社であるアップルやグーグルの株価はそのように振舞っている。
企業価値がオーバーバリュー気味に見えていても、それでも値崩れしないでしっかりしているのは、それだけ将来の利益見通しに自信があることの現れなのか、それともいまだに中途半端な正常化しかできていない金融政策のたまものなのか。
これは時間がたってみないとわからないことだ。北朝鮮問題で揺れることがあっても、地政学的リスクの高まりで株価が安くなったところは絶好の買い場だという奇妙な自信まで出てきている。
米国株は世界のベンチマークなのだから、それにつられて各国の株価も高騰せざるをえない。ドイツ株は相当に買い進まれており、ECBの金融政策が生ぬるいことをドイツの関係者が口にしだしている。株価高騰はリスク許容度の増大によるものと決めつけているようだ。
確かにPERなどは異常に高くついている。つまりねん出する利益が株価に見合っていないということ。将来に稼ぐであろうという思惑だけでは説明できなくなっていることへの警鐘でもあるのだろう。
日本株も例外ではなく、日経平均は23000円台に乗せてきたりした。これは1990年から日本株が下落して、1992年に14000円台までドロップしてからのマックス戻しが1996年の22666円だったことを考え合わせると、バブル後のすべてのシコリが解消したのだとも見られる水準だ。まだ終値ベースでは23000円台を実現していないが、目先は足踏みしている。
日本時間 16時00分
| 【2026年2月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年2月2日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!

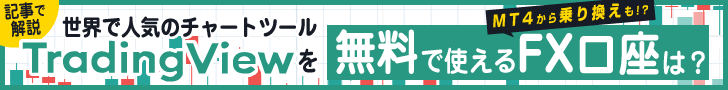
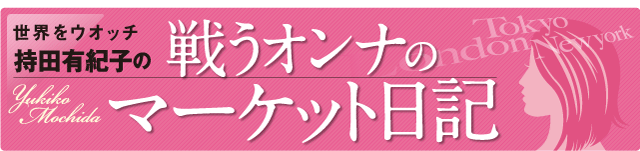
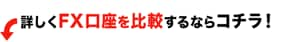
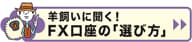



















![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)







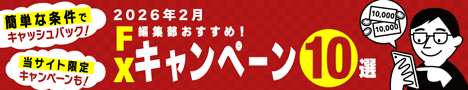
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)