週明けの月曜日は日本と中国が休みだったので、マーケットの動意は薄い。しかし週末に中国がアメリカとの交渉をキョゼルしているという報道が成されたことで、リスク回避の方向で始まった。動きがないまま海外市場にシフトしていったが、ドラギ総裁のインフレ発言でユーロが急上昇する局面があった以外には大きな動きはなかった。
注目は国連総会に合わせてニューヨークに集まってきている首脳会談に移っている。日米の貿易協議が1日延期されるというハプニングが起こったが、それがどのような思惑を引き起こすのか。今日のマーケットの材料になるだろう。
ところで足下で貿易戦争が起こっているが、これは言うまでもなくGDPの押し下げ要因であり、物価の上昇が消費者マインドも冷やす。ファンダメンタルズ的にはリスクテークしているどころではないのに、現実は米国株などは9月に入ってからも史上最高値を更新してきたりしている。
日本株も実体がない割には日経先物が24000円台を目指す動き。そしてBREXITがハードなものになるかもしれないと危惧されているイギリスの通貨も、それほどもクラッシュしていない。
要はマーケットの悪材料を完全に無視して見ないことにしているのだ。相場に反応が現われてこない以上、すなわち株価の下落や通貨の下落が見られないので、誰も考慮しなくても良いと思いたいのだろう。
しかしよく考えてみれば2001年の飛行機が落ちたときも、2008年のリーマンショックのときも、市場に現われるまで1年以上もかかっているのが事実だ。2001年のときは確かに米国市場が1ヶ月ほど停止した。しかし12月には早くもテロ以前の水準まで株価は持ち直している。
日銀の介入もあってドル円は115円割れから、一気に130円台まで吹き上がった。それでもファンダメンタルズの低下は避けられず、アメリカ主導の戦争が近づくにつれて、1年以上も遅れてマーケットは激しいリスクオフにさらされた。
2008年の時も同様で、端を発したのはサブプライムローンである。これは2007年の2月にグリーンスパンが指摘したものだ。それから夏場にかけて欧州の銀行などで損失を計上することもあったが、一時的なリスク回避でとどまった。市場参加者も固有の問題として起きたかったのだろう。年が変わって米系の金融機関に損失が出だしても、ショックはそれほどもなかった。
ベアスターンズは破綻したが、公的資金で救済されたのである。市場はますます安心感からリスクテークに走り、夏には原油価格は140ドル台へ、ユーロ円は160円台を記録した。世界的に株価も高いまま。
それで訪れた9月のリーマンショック。リーマンは救済されなかったのである。何もファンダメンタルズは変わっていないのに、サブプライムを問題視しての魔女狩りが始まった。だからこれも市場の反応を見るまでには1年半もかかったことになる。
市場が混乱に陥るのがいつなのかはわからない。しかしかなり遅れてでも、やはりファンダメンタルズに従わないといけない時期がやってくるのだろう。
日本時間 15時00分
| 【2026年1月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年1月5日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!

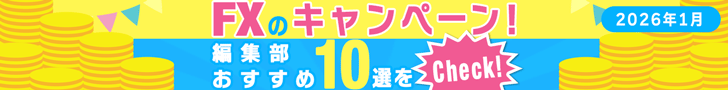
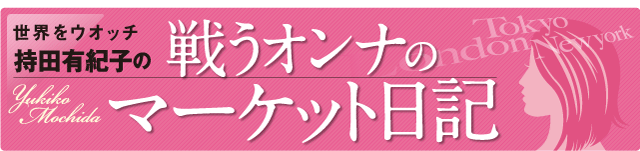
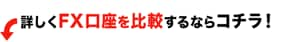
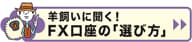



















![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)








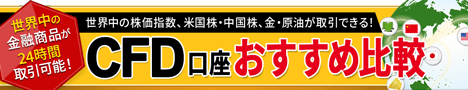
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)