夜中の要人発言では、ブラード総裁が「次のアクションは25ベーシスポイントの利下げだけでよい」といったことで、ハト派の姿勢がやや弱まった。そしてパウエル議長のトークでも、やはり利下げ期待の高まりを抑制する方向の発言をしている。これをうけて過度に高まっていた早期の利下げ期待は薄らいだ。
それまで売り込まれていたドルに大きく買い戻しの機運が戻った。しかしドル円もユーロドルもドル高の方に向いたのだが、ドルの上値は限られていた。ニューヨーククローズに至るまでに、ドル円は再び軟化し、107円ちょうどを割れそうなところまで落ちてきている。
利下げ期待が強すぎたのは、パウエル議長の指摘する通りだ。「短期的な見方やデータにはスタンスはブレない」というのも、金融当局者としては当然に姿勢であろう。しかし問題は残る。7月に利上げするには、6月で何もしなかった理由も説明できなくてはいけない。
また次回の9月まで待てなくて、なぜサマーバカンスに入っている時期に利下げするのかについての説明も必要だ。それを十分に満たしてくれるだけの根拠は何が出てくるのかどうか。
確かに月末にG20が控えているので、その結果を見たいという気持ちもあろう。しかしトランプ政権の姿勢はマルチラテラルな会合よりも直接の2国間協議を優先しているのは明らかだ。それゆえのTPP離脱でもあったろう。米中協議はG20の場で解決されるべきという意気込みは、アメリカ側には少ないはずである。
そのようなものの動向を待っているというのはおかしな話しでもある。途中に出てくる経済データで重要なものは、雇用統計が1回分とGDPの速報値である。果たしてこれだけでペースを守らないで金融政策を変えさせる材料になるのかどうか。
米企業決算が7月中旬から本格化するが、これを見てからと言うのはマクロ経済を操る当局者の取るべき施策とは言えないだろう。先行する様々なマクロ指標で判断して企業業績を見通すくらいでないと、金融政策を打っても後手に回るだけで効果は少ないものとなろう。
最後にイランとの紛争があるが、戦争が起こるのを期待しているわけではないのだから、これに対して「予防的な利下げ」をするのは、あまりにも政治面に迎合が過ぎると批判を浴びることにつながる。
ともかくもFRBが7月利下げを正当化する根拠が薄弱な分だけ、マーケットの不透明感が高まっているとも言える。現在は米国株がまだ高いところに張り付いているので問題視されないが、何かのきっかけで株価が崩れる兆候が見え始めると、FRBは困難な市場運営を強いられることになりそうだ。
日本時間 15時00分
| 【2026年1月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年1月5日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!

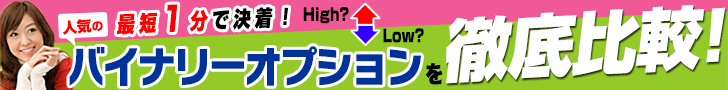
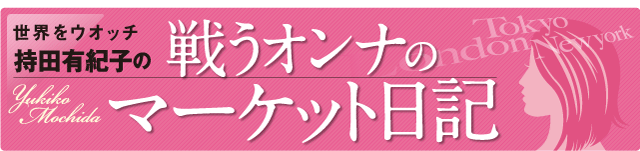
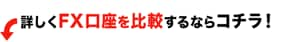
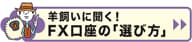























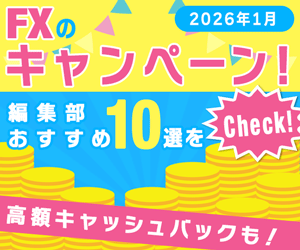



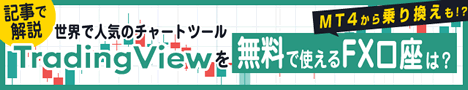
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)