昨日のアジア時間ではリスクテークの動きが高まった。その前日には米国株が大幅安しているにも関わらず、日本勢が「安いから買う」という姿勢を崩さなかったためだ。日経平均は朝から500円以上も急上昇して、ドル円も110円台の後半で始まったものが111円台を回復したりしている。
これでややダウンサイドリスクが薄まったかに見えたマーケットだったが、ニューヨーク時間では米国株は大幅安したことでマーケット全体がリスク回避の姿勢が強まった。ドル円も110円台のミドルでかなり粘ったが支えきれず、夜中には109円台にも突入している。
アメリカのCDCが国内でのウイルス感染に注意を喚起したということもあるが、なんで連日での大幅安を演じることになってしまったのか。売り切れていなかったのか。
リスク回避の局面では、安全資産とされる米国債などが買われることになる。そして昨日は10年ものの利回りは1.3055%まで下げてしまった。これは過去最低の記録であり、2016年の夏場につけた1.3180%を下回るもの。BREXITの国民投票よりも、コロナウイルスの感染のほうが破壊力があるということだろう。
記録を更新したというと大きな動きにさらされたみたいな感じに陥るが、実際にはそれほどでもない。ダウ平均が1000ドル級の下げを2日連続でやってしまうくらいの恐怖感であれば、普通ならば10年債の利回りが300ベーシスポイントくらい下がっても不思議ではない。それが100ベーシスも下がれないのだ。これはやはり金利商品が金融マーケットの中でワークしていないということだろう。
オバマ政権の第2期から、またはバーナンキ議長の任期の最後あたりから利上げを始めるべきであった。ダウ平均が2万を超えて来ても何もしなかった。またダウ平均が3万に近づいているというのに、いまだに金利を下げることしか頭にない。従来の教科書では説明しきれないことをやってきたのだ。
ドル金利は下げても、その下げ余地は少なく、マーケットに足元を見られている。質への逃避で債券を購入しても、そんなに利益が出ないのならばヘッジとしてリスク回避しても穴埋めはできない。リスクヘッジが効かないとなったら、自分が持っているそのものを売るしかない。それが今週の株式相場の大幅安となって世界中に起こってしまっていることなのだろう。
またFRBの副議長は「市場は利下げを織り込んでいるが、まったくの不自然」などと言っているのもおかしい。「市場との対話」を拒否している姿勢のようだ。市場のほうが先走ることがあっても、それを自分らの写し鏡だと思って政策当局者は行動しないと、市場からの信頼をなくすのである。
ともかくも株売りはダイレクトに出てくる状態が続きそうだ。米国株の先物取引で最大の取引量を誇るのはミニS&P先物だが、これが昨日は400万枚の出来高を誇っている。これは今世紀に入ってから最大ではないだろうか。今まで見たこともない。
激しかったときでも300万行くのもやっとだ。ともかくも出来高を伴った株価の下げである。当面はリスク回避の方向についていくしかないだろう。ドル円やユーロ円は戻り売りスタンスで臨む。
日本時間 15時00分
| 【2026年2月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年2月2日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!


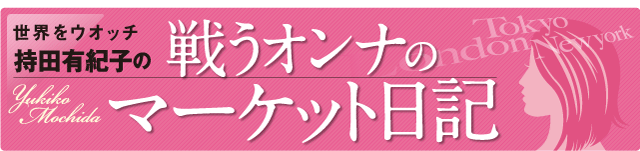
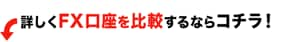
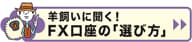


















![トレイダーズ証券[みんなのFX]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C14464&lc=PAN1&isq=130&psq=0)
![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)








株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)