昨日のアジア時間ではややリスク回避の動きが先行した。それが昼間の日銀会合へ向けての期待が必要以上に高まったことによる。どうせ何も日銀はアクションを起こさないだろうというコンセンサスダルにも関わらず、なぜかいつも発表の直前で期待の高まりで株高や円安を演じてしまう。わかっていても期待してしまうのだろう。
そして結果が出るとリスク性の高いものは持ってはいられないということで、株価やドル円は下がってしまう。昨日もドル円はあっさりと119円台に突入し、119.40あたりまで差し込んだ後は、なかなか値を戻さなかった。私も119円台は買いだなと考えていたのだが、そうした連中の買い意欲をそぐほどのドル円の重さ。そして株価の値の戻りの鈍さであった。
先日のG20で始められた議論ではないが、通貨安競争が問題になっている半面、通貨安が防げないこともまた問題になりつつある。トルコやロシアは言われていて久しいが、先週あたりから問題視されてきたのがマレーシアである直接の原因は政治家、特に現職の首相の汚職にあるようだ。それで通貨リンギットの価値下落に歯止めがかからないようだ。しかもマレーシアは資源国として通っている側面も大きい。昨年の後半から続いている資源安をモロに影響を受けている国なのだ。
そのマレーシアは1997年からのアジア通貨危機の際に、マハティール首相の指導で通貨を完全にドルペッグにしたことでも有名だ。それは自国通貨を無制限に買い支えてでも、通貨安にはブレさせないという決意表明のようなものだが、当時はうまくワークしたのに、今回のマレーシアには通用していない。対ドルでも為替レートは4の大台を超えてきた。そろそろ新聞などでも指摘が増えはじめている。
ここで優等生だったマレーシアがどうしてこんな状況になったのかの遠因を考えてみると、やはり中国の景気減速に行きつく。需要低迷は資源の価格を押し下げ、また地理的にも中国経済圏に組み込まれていることも中国のスローダウンの余波をまともに受けてしまう。国内政治の不安定かはマレーシア独自の問題だが、それが背中を押しているという形になっている。
中国経済の動向に振らされているマーケットがここ2か月間もの間、続いているが、それは周辺諸国へも波及して広がりつつある。だから今回のリスクオフの流れは決して一時的なものではない。これを為替相場のなかで見ていくと、いかに日銀が追加緩和をしたり、日本政府がアベノミクスを強調したところで、グローバルな経済の中では通用しないことになるだろうということを考えねばならない。
日本時間 11時30分
| 【2026年2月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年2月2日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!

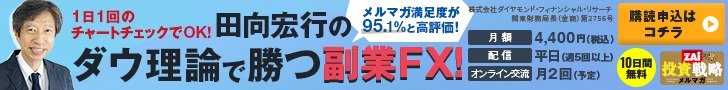
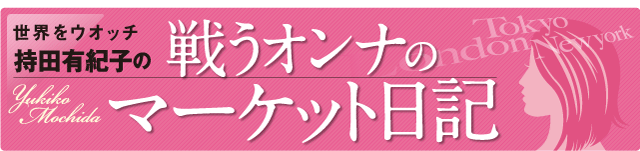
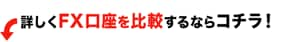
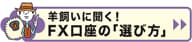


















![JFX[MATRIX TRADER]](/mwimgs/1/1/-/img_11ea8f72aab2277adcba51f3c2307d8210084.gif)
![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)
![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)








株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)