■一番のサプライズは市場の反転スピード!
トランプ米大統領の誕生で、サプライズの連続があった。そもそも、トランプ氏が当選すること自体がマーケットにとってサプライズであったが、さらに市場関係者を驚かせたのが、その後のマーケットの反応だった。
筆者にとっては、いわゆる「トランプ・ショック」がもたらした市場の急落自体は当然視していたから、まったく問題ではなかった。
また、その後の米国株をはじめとしたマーケットが回復し、逆に高値を更新していくことも、今まで何回も経験してきたから、それほどサプライズとは言えなかった。
しかし、何より驚いたのは、その反転のスピードだった。
開票日の11月9日(水)に、NYダウ先物は時間外で約5%も下落していたが、ニューヨーク時間では主要3指数(NYダウ、ナスダック、S&P 500)がそろって大幅高となり、結局、NYダウは1.4%高で大引けとなった。

(出所:CQG)

(出所:CQG)

(出所:CQG)

(出所:CQG)
■日足で見ると、さまざまなチャートがヒゲだらけ!
それとリンクした形で、米ドル/円は101.16円まで売られたものの、結局、11月9日(水)当日は105.90円まで反騰し、7月27日(水)以来の高値をつけた。
そして、当日(11月9日)の始値が104.97円だったから、日足のチャートは長い「下ヒゲ」をつけた反転となり、その「下ヒゲ」の部分が、昨年(2015年)の「人民元ショック」の8月24日(月)よりも長かったことに、実に驚いた。

(出所:CQG)
米ドルの対極として、ユーロの値動きはもっと激しいものだった。ユーロ/米ドルはザラ場高値の1.1299ドルから1.0904ドルまで急落、そして、当日の始値が1.1018ドルだったから、日足では長い「上ヒゲ」をつけた大陰線となった。やはり、こんなに長い「上ヒゲ」は、近年まれに見るものだ。

(出所:CQG)
同日に同じ長い「上ヒゲ」をつけたゴールドの日足も印象的で、総じて米ドルの強さを証左している。

(出所:CQG)
当然のように、一昨日(11月9日)のドルインデックスは長い「下ヒゲ」を持つ陽線になった。大引けした際の足型自体も、なかなか見事というか、滅多に見られないチャートであった。

(出所:CQG)
■トランプ・ショックどころか、トランプ・バブルの様相
今となって、なぜこのような激しい反転がみられたかについて、多くの解釈が行われたが、後解釈にすぎないと思う。というのは、市場自体のパフォーマンスからしても、事前のセンチメントにしても、そもそもトランプ氏の当選が予想されていなかったから、今さら「トランプ・ショックが一時的」云々と言っても説得力に欠ける。
ただし、後解釈でも正論であるなら、聞いておく価値はある。
いろんな解釈があったものの、要するにトランプ氏は積極財政スタンスを表明していたから、経済成長やインフレへの期待が高まり、株が買われ、債券が売られたということだ。米10年物国債の利回りは大きく上昇し、2016年2月以降ではじめてハッキリ2%を超えた。日米金利差の拡大が米ドル高・円安につながったのも当然な成り行きだという。

(出所:CQG)
この勢いでNYダウは昨日(11月10日)、史上最高値を更新し、「トランプ・ショック」どころか、「トランプ・バブル」の様相を呈している。

(出所:CQG)
が、勝ち組の米国株の中、ナスダックの下落が目立ったように、明暗が分かれたものもあったから、トランプ氏の政権運営に市場の期待と不安が入り混じっているとも読み取れる。

(出所:CQG)
■本当のトランプ・ショックはこれからか
そもそもトランプ氏は商売人ではあるが、政治家としての経験はまったくない。氏の政治理念や政策主張、過激というか、幼稚というか、現実に通用するかどうか、まったく未知数のところが多く、マーケットが急回復したのはトランプ政権に安心したためという解釈は性急であり、また、いくぶん滑稽に聞こえる。
今回の米大統領選は、米国史上もっとも見苦しい選挙で、また、有権者がもっとも分裂した選挙と言われたばかりだったのに、選挙が終わった途端、すべてが安心できるわけがない。
安心したところがあるとすれば、当選したあと、トランプ氏が今までの主張をいったん封印し、「大人」としての穏やかな口調(氏にふさしくないとも言える)に終始したことのみではないだろうか。
が、これからトランプ氏が従来の過激な主張をまったく言わなくなることも想定しにくいから、この意味では、本当の「トランプ・ショック」はこれからだとも言える。だから、目先のマーケットの安心感がホンモノかどうかは極めて疑わしいものだ。
■前例を学習した結果が今回の市場の反応?
昨年(2015年)8月の「人民元ショック」にしても、今年(2016年)6月の英EU離脱にしても、米国株のパフォーマンスに限って言えば、いわゆるショックを克服する強さがあった。それが「慣例」になったことが、今回の市場の反応につながった要素として大きかったのではないだろうか。

(出所:CQG)
言い換えれば、目先のマーケットの反応、トランプ政権に対する信頼云々よりも単にマーケットが学習して、経験上の行動パターンをまた繰り返しただけなのではないだろうか。この意味合いからも、目先のパフォーマンスと中長期の展望は分けて考える必要があると思う。
■市場の動きに感じる2つの矛盾
そもそも、この2日間のマーケットのパフォーマンスに矛盾を感じたところも多い。
1つはインフレ期待が高まっていると解釈される一方、金が急落していることだ。こうなると、インフレ期待が本当に高まったのか、疑わしい。なぜなら、インフレにもっとも敏感なのが金のはずだからだ。
金の急落は単純に米ドル高がもたらした結果なのか、それとも構造的にいわゆるインフレ期待を否定しているのかを見極めるべきだ。

(出所:CQG)
もう1つはもっと単純明快だ。インフレ期待がもたらした米金利の上昇がホンモノなら、それが史上最高値を更新し続けている米国株「バブル」を助長するのではなく、とどめを刺す役割を果たすはずということだ。
現在のように、米金利上昇や米利上げ期待が株高の背景として解釈されることは普通ではない。果たして、このような市況が続くかどうかもかなり疑問だ。
このように、この2日間のマーケットの激動は、深思熟慮した市場参加者の決定よりも、学習効果を出てきたヘッジファンドやアルゴリズム取引に主導された短期売買が作った一時の現象、という公算が大きい。
ウォール街の連中の多くは、トランプ氏の当選さえ予測していなかったし、また、氏の主張や政策を散々批判するどころか、かなり馬鹿にしてきただけに、目下、心からトランプ政権を歓迎しているわけでもない。表向きだけ、一時のユーフォリア(熱狂的陶酔感)を演出したにすぎない。
■米ドル/円は最大110円まで上昇後に100円まで下落か
だから、市場が再び反転するのを警戒しておくのが正しいスタンスであろう。が、米ドル/円に限っていえば、これから再度100円の大台打診ありといった従来のシナリオを維持する一方、足元の米ドル高・円安のトレンドが反転する前に最大110円の打診を警戒しておきたい。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 週足)
その理由と詳細はまた次回。市況はいかに。
(14:00執筆)

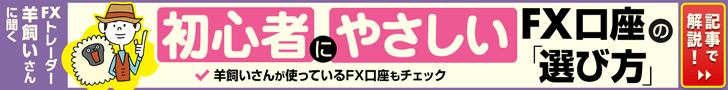












![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)
![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)








株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)