為替マーケットは一進一退を繰り返している。ドルインデックスは6月19日(火)に81.18まで下落したものの、6月21日(木)に急騰し、82.40の手前まで迫った。

(出所:米国FXCM)
このところ、2大イベントを通過して、どちらかというと無風状態だったのだが、6月21日(木)の米国株急落で、再び嵐が吹き始めた感じだ。
まず、週明けの6月18日(月)にギリシャ再選挙の結果が判明し、市場コンセンサスと違って、ギリシャの穏健政党は過半数を確保、6月21日(木)には三党連立政権が正式にスタートした。
選挙前、ギリシャのユーロ離脱必至といった予測が圧倒的に多い中、あえてそうではないと思わせる節があり、それを看過できないと筆者は思っていたため、ギリシャのユーロ離脱観測にかなり懐疑的だった。
■ギリシャのユーロ離脱は「原子爆弾」級の脅威
その「節」とは、ギリシャとEU(欧州連合)の攻防がかつての冷戦構造と似ているところだ。
冷戦構造をもたらした大きな背景として、核戦争の脅威による力の均衡がある。
つまり、戦争に突入できなかったのは核戦争への恐怖、そして、「最後には誰も勝てず、皆が負けてしまう」という予想だ。こういった恐怖と予想によって戦争の衝動が抑えられ、冷静な判断が下されてきたわけである。
ギリシャは小国でありながら、今はまさに「金融爆弾」となり得る。ギリシャがユーロを離脱すれば、自らの混乱と衰退はほぼ確実であるが、EU側にも莫大な損失を与えるから、その脅威も「原子爆弾」級だ。
保守的な計算でも、ギリシャのデフォルトがあれば、EUに少なくとも3500億ユーロの損失を与えるはずだ。それはギリシャ援助金に加え、ギリシャ債券および銀行団の融資など多岐に渡る。ECB(欧州中央銀行)を始め、EUが抱える債権はすべて焦げついてしまうだろう。
よりインパクトが強いのは、ユーロ離脱を簡単に許してしまうと、ユーロシステムそのものへの懐疑論が助長され、それがユーロ崩壊の始まりになりかねないということだ。
通貨はしょせん「紙」であるから、信頼感がなくなると、意外に早いスピードで崩壊してしまうことは歴史的に証明されている。
今、問題視されているスペインやポルトガル、さらにはイタリアなどの「デフォルト予備軍」が控えているだけに、ギリシャの離脱は安易に許すことはできない。
■ギリシャがユーロを離脱すれば、悲惨な末路が待っている
一方、当のギリシャはユーロ離脱を選択すれば、国家をまとめられないか、国家は存続しても誰からも相手にされず、かつてデフォルトしたアルゼンチンより悲惨な末路が待っていることはもはや自明の理である。
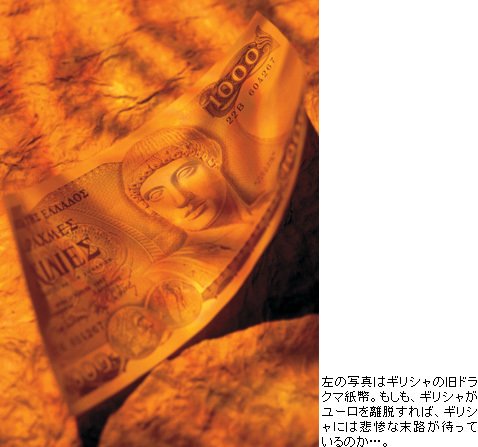
天然資源を持たず、根幹産業も育たなかったギリシャは「中世」に逆戻りしてしまうといった予測さえある。
最悪の結果を防げたのは結局、冷静な判断であり、冷静な判断を迫った背景には実は恐怖心が働いている。
こういった冷戦時代に示された有益な教訓は現在でも通じるはずである。
だから、あのリーマン・ショックの再来、金融大崩壊前夜の雰囲気が濃厚になってくればくるほど、恐怖感が高まってくるから、逆に関係国は自制し、政治家、国民が冷静な判断を下せる確率が高まってくるのである。
今回、ギリシャ国民の判断は、まさにそういった「恐怖心を抱えた正しい判断」となったわけだ。
■米国株急落とドルインデックス急騰をもたらした原因は?
次にFOMC(米連邦公開市場委員会)の結果だが、こちらはほぼ市場予想どおり、FRB(米連邦準備制度理事会)はQE3(量的緩和策第3弾)の発動を見送り、年内一杯、「ツイストオペ」を延長するに留まった。
FRBは、必要に応じて一段の措置を講じる用意を改めて表明したものの、大統領選が本格的シーズンに突入する年後半になると、よほどのことがない限り、新たな措置は講じられないとみられる。事実上、年内一杯は新たな措置を講じることができないだろう。
こういった見方や思惑が6月21日(木)の米国株急落とドルインデックス急騰をもたらしたのではないかと思う。

(出所:米国FXCM)
なにしろ、先週(6月11日~)からマイナス材料が続出しており、世界的な景気減速懸念が強まる中、FRBの「年内静観」といったスタンスが市場の不安を増大させている側面は無視できない。
米国では、新規失業保険申請件数が市場予想を上回り、フィラデルフィア連銀製造業景気指数はかなり悪化し、中古受託販売数も減少した。
EU、中国も含め、世界的な製造業活動の低下が懸念されている。それに加え、EUではスペインの銀行支援問題など危機がくすぶる。
さらに6月21日(木)にはゴールドマン・サックスのアナリストが株式の空売りを推奨、ムーディーズがクレディ・スイスの格付けを3段階格下げするなど、大手銀行15行の格下げを行ったこともマーケットの心理をさらに冷え込ませた。
要するに、6月21日(木)のマーケットの反応はFRBの政策への失望に加え、マクロからミクロまで、悪材料が重なってきた結果である。
■リスク回避の動きはこれからも強まっていくのか?
短期スパンでは、こういった市場心理を重視すべきだが、中期スパンでは、こういった動きは一時的で、リスク回避の動きがこれからも強まっていくかどうかを見極める必要があると思う。
確かに、FRBはQE3を見送った。しかし、量的緩和やゼロ金利自体は変わらず、有事の時にはQE3に踏み切ることも公言している。
EUの利下げも想定される中、中国の利下げ実施に加え、世界的に量的緩和が進んでいる環境下で、欧米株の下値余地は限定的ではないかとみる。
EUのスペイン問題も引き続きマーケットを混乱させる可能性が高いものの、基本的にはパニック的な反応は起こらない可能性が高いと思う。
こういった見方を証左する指標は2つある。
1つは円のパフォーマンス、もうひとつはVIX指数だ。
リスク回避の値動きがこれからも強まっていくのであれば、ドルインデックスの上昇とともに、足元で円は売られるのではなく、買われるはずである。
米ドル/円の80円台乗せ、ユーロ/円の101円の節目突破はリスクオフの視点からは説明しにくい。
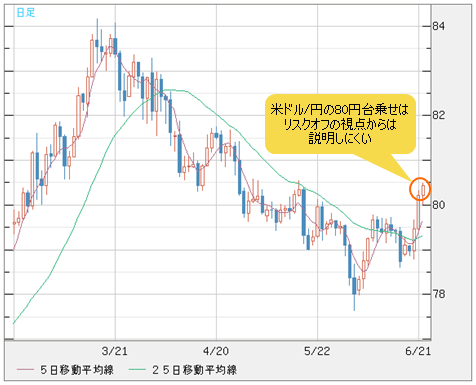
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足)
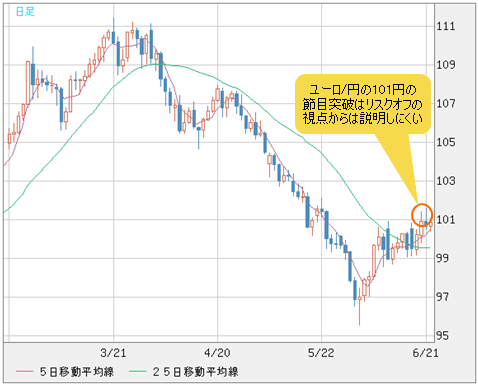
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/円 日足)
また、VIX指数(※)は20前後のレベルを示しており、安定した水準に留まっていることも証左する材料となる。
(※編集部注:「VIX指数」はS&P500指数を対象としたオプション取引のボラティリティ(変動性)を元に算出されている指数。「恐怖指数」とも呼ばれており、投資家の不安感が増大すると、数値が上昇する傾向がある)
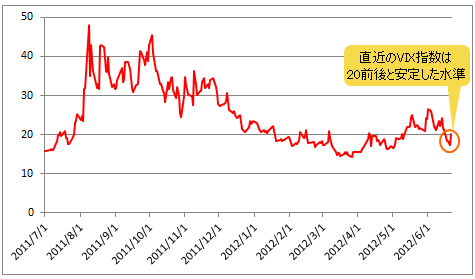
詳細はまた次回に。
(6月22日 14:00執筆)

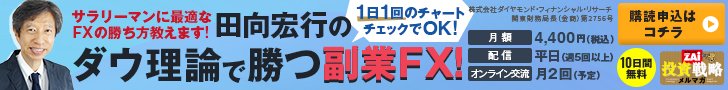











![JFX[MATRIX TRADER]](/mwimgs/1/1/-/img_11ea8f72aab2277adcba51f3c2307d8210084.gif)








株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)