■円安のクライマックスは近い! その根拠とは?
米ドル/円は107円台前半まで上昇している。前回のコラムを書いた際、105円台後半に位置していたから、前回の見通し、すなわち「1円~2円の上昇余地」で測ると、目先は「いいところ」に来ている。
【参考記事】
●ドル/円はもう1~2円上値余地はあるが、10円超の本格調整ありという見方は堅持(2014年9月12日、陳満咲杜)
もちろん、この「いいところ」とは円安のクライマックスが近いという意味合いで、2011年10月末につけた米ドルの史上最安値を起点とした、大型上昇波の最終段階を意味する。
したがって、本格的な円高調整も間近であろうと思う。
(出所:米国FXCM)
テクニカルの視点では、この「いいところ」は上のチャートにて確認できる。2010年5月高値から2013年5月高値を連結するレジスタンスラインが2014年年初の高値を制限していたように、目先もレジスタンスラインとしての役割を果たす公算が大きいだろう。
さらに、RSIで見る大型弱気ダイバージェンスはなお継続しており、前述の見方と整合させると、米ドル高が強くても、目先の節目にていったん頭打ちになっても不思議ではなかろう。
■米ドル/円の上昇についていかない日経平均
もっとも、ここに来て、円安加速論が主流となり、株高・円安をセットにした考え方も一層盛り上がっている。日経平均は、1万6000円の大台の手前に来ているから、セットにした相場の展開も想定されやすいところがある。
しかし、よく見てみると、なんとなく違和感が出てくる。
アベノミクスが始まって以来、米ドル/円と日経平均はほぼ連動した形で高値、安値を形成してきたが、米ドル/円が6年ぶりの高値を更新しているのと対照的に、日経平均は、現時点で2013年年末の高値(1万6320円)までなお300円以上の距離がある。
こういったギャップを一種の「ダイバージェンス」とみなした場合、これからこれが修正されていくかどうかは重要である。
(出所:米国FXCM)
要するに、近々日経平均が高値更新し、米ドル/円の値動きを追随するか、それとも米ドル/円が反落し、日経平均の鈍さに反応した形を取るかによってしか、両者の「ダイバージェンス」の解消は図れないので、興味深いところなのだ。
とはいえ、一般論として為替と株式の連動は、常に相関性を持つとは限らないから、こういった見方、常に適用されるとも思っていない。
しかし、上のチャートで示すように、アベノミクス相場が始まって以降、米ドル/円と日経平均の連動性はかなり大きかったから、日本株上昇の原動力は、ほぼ円安によるものと見ても大きな間違いはないだろう。
ゆえに目先、米ドル/円の高騰にあまりついていかなくなっている日経平均が、なんらかのメッセージを出していると考えても杞憂ではなさそうだ。
■「アベノミクス円安第二弾」はもう織り込みずみか
「ダイバージェンス」はもう1つ、米ドル/円のクロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)との相違からも測れる。クロス円といえばユーロ/円が代表的な存在なので、ユーロ/円を見てみよう。アベノミクスが始まって以降、2013年年末までは、米ドル/円との連動性もかなり高いことがわかる。
(出所:米国FXCM)
「ユーロ/米ドルがこんなに下げているから、ユーロ/円が米ドル/円についていかなくなっているのは当然だし、何が問題なのか」といった反論も容易に推測できるが、強調しておきたいのは2013年年末・2014年年始までの円安と違って、目先の米ドル/円における円安進行はほぼ独歩的で、整合性を保っていないところだ。
換言すれば、巷でささやかれる「アベノミクス円安第二弾」は、あっても現在の米ドル/円のレートに織り込まれており、なかなか再来しにくいのではとみる。
黒田日銀総裁は最近、また量的緩和の可能性をほのめかしており、安倍内閣も大型財政出動を検討していると聞く。
しかし、やや独断的にいうと、これは本質的にはすべて次回消費税増税への道づくりで、従来のアベノミクスとは異なる性質を持つものだから、マーケットには本格的な影響を及ぼせないとみる。
第2四半期GDPの再度下方修正に見られるように、アベノミクス第二弾どころか、「アベノミクス第一弾」自体の限界がそろそろ露呈し始めているから、これはいずれマーケットに検証され、また、その結果が織り込まれていくだろう。
■外部要素の悪化をマーケットが織り込み始めた
より大事なのは、本コラムがたびたび強調してきたように、アベノミクスが実質的には一本の矢(日銀量的緩和)しかなく、また、成功したところがあれば、外部要素の良さに恵まれてきたところが大きいということだ。
前述のように、2013年年末~2014年年始ごろまで、米ドル/円と日経平均、そして、米ドル/円とユーロ/円が高い連動性を示してきたのはまさにその象徴であり、こういった連動が崩れている現在は、外部要素の悪化をマーケットが織り込み始めたと言えるだろう。
為替マーケットにおいては、外部要素の悪化はまず、ユーロと英ポンドの大幅反落に表れているだろう。
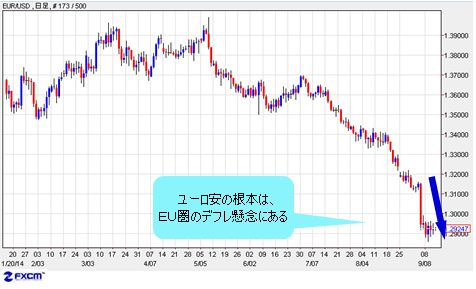
(出所:米国FXCM)

(出所:米国FXCM)
ユーロ安の根本にはEU(欧州連合)圏のデフレ懸念があり、英ポンド安の背景にはスコットランド独立問題やEU離脱の有無といった懸念がある。
そして遅れた形で、商品相場の総崩れとあいまって、豪ドルのリバウンドも終了し、これから安値トライをしていくとみる。
言い換えれば、目先の米ドル高は、必ずしも米サイドのファンダメンタルズの良さに起因しているとは限らず、外貨サイドのファンダメンタルズの悪化が大きな原因となっている。外貨安の受け皿として必然的に米ドル買いにつながっているから、従来のようなリスクオン一辺倒の状況とかなり異なっているのだ。
こういった状況の中、はたして円安がこれ以上進むかというと、筆者はかなり懐疑的で、おのずと限界に来ているのではないかと思う、はたして市況はいかに。
(14:00執筆)

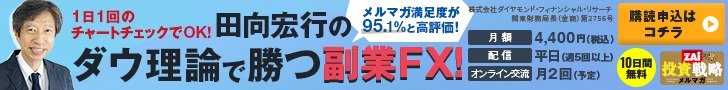


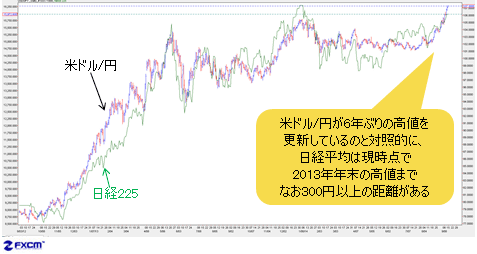
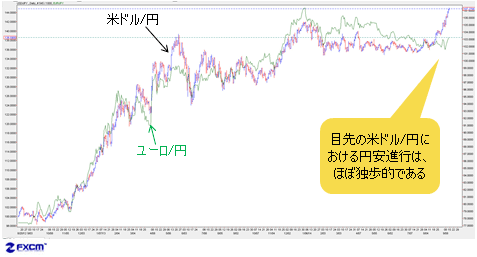










![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)
![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)







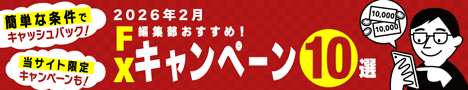
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)