昨日はアメリカが連休で休みなので、どうせマーケットは動かないだろうと思って、私もまったくマーケットを見ないで休んだ。「休むも相場」である。翌朝になってから動いているようだったら、そこからポジションを張っていっても遅くはないと思うのである。
昨日はトルコのCPIが発表されたが、17.9%だった。今回のCPIによって10日後ほどに控えた金利会合では、利上げしないといけないことがほぼ確実になった。あれほど政権側が利上げを嫌がっていても、市場が催促するという形になりそうだ。
しかしこのCPIはものすごく高いとはいえ、PPIはすでに30%台に達しているのだ。PPIはCPIに3ヶ月ほど先行するとされる。だから今回のCPIに合わせて利上げするというのは金融政策を間違った方に導くことにもなろう。
インフレ率の度合いはもっと激しく上がるのである。先を見越したような利上げを適宜に行わないと、利上げ自体が物足りないものと解釈され、それがさらなる通貨安をもたらすことになる。新興国不安の増大を引き起こす景気になるかもしれない。
トルコの通貨安はマーケットの不安材料であることに違いはないが、ケタはずれに混乱をきたしているのがアルゼンチンやベネズエラといったハイパーインフレに見舞われている国である。インフレというのは通貨価値の減退を意味する。物価高のことを指すと言っている学者風情な人もいるが、物価高は通貨価値の変動による結果の一側面でしかない。
インフレを抑制するには金利を上げるというのが短絡的な処方箋として考えられているが、利上げしたからといって通貨価値が素直に上がっていくものではない。先日、アルゼンチンは政策金利を45%から60%に利上げしたが、ここまで上げ幅が大きいと果たして金利そのものに意味があるのかどうか。
通貨価値の減退が進むということは、貨幣が紙くずになってしまうことを意味する。誰も対価としてお金を受け取らなくなる。そうすると物々交換のほうが交易の信頼性が高いということになり、現物を持っているのがインフレに強いと言うことになる。
実際にアルゼンチンやベネズエラで起こっていることを見てみれば、公共の場からはほとんど物品が消え去ってしまっている。言うまでもなく窃盗など犯罪によるものが大半だ。消防署や公民館病院といったところからはイスやテーブル、パソコンなどの電気製品はもちろんのこと、カーペットや水道管まで、お金になりそうなものはみんな持っていかれているようだ。
インフレの芽は出ていたはずなのに、それを「兆候は見えない」などと言って慰め合っていたものだから、無策に時を過ごしてしまった。困るのはいつの時代も老人と子供、病人である。日本も笑ってはいられない話しである。
日本時間 15時30分
| 【2026年1月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年1月5日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!


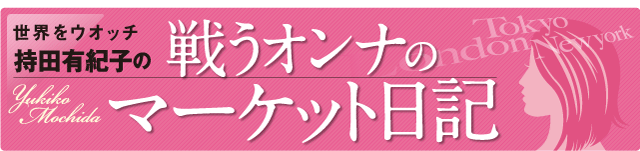
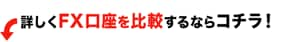
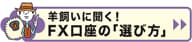


















![トレイダーズ証券[LIGHT FX]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C14464&lc=LFX1&isq=301&psq=0)









株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)