株価はEPSとPERをかけ算したものである。一株あたりの利益の額がEPSであり、それを何回分だけ回収すれば株価の元を取れるのかというのがPERである。だから株価が上昇するときは、EPSが上がるかPERが上がるかのどちらかになる。
EPSは利益だから比較的、定量化しやすいし、近い将来の予測もしやすい。一方でPERは過去の平均でどうだったかということくらいしか参考にならない。PERは15倍くらいが普通の状態だと言われている。
そして今年の2月に米国株が史上最高値を記録しているときは、20倍近くもあった。これは足下で捻出されている企業利益に対して、期待だけが大きく先行しているということを表す。
現状ではロックダウンもあったことだし、企業利益は大きくへこんでいる。将来のEPSの回復見通しには明るいものがあるが、足下では米国株のPERが25倍まで膨れ上がってきている。これが期待先行ということで解釈すればいいのだろうか。
それとも単に割高なのを承知していて、それでも投資家がリスクテークしたくてたまらないことへの証明なのか。それは時間が経ってみないとわからない。こうしてわからない状態が続いていると、為替相場でのリスクへの反応もしょぼいものに終始してしまうことになるだろう。
ニューヨーククローズ後にFRBがストレステストの結果を公表した。いずれの銀行も自己資本は最低限を満たすというものだった。従来のストレステストにおいては最大の負荷をかけたリスクを想定していなかったのが、まさか全都市がロックダウンすることまでは想定しきれなかったということだろう。
資本は問題なくとも、企業利益が大幅に後退している。それゆえに配当の禁止と自社株買いの停止を強制することとなった。利益が出ないどころかマイナスなのだから、EPSからかんがみても余裕があるはずはない。
銀行ですらこうなのだから、他の一般事業会社ではなおさらである。これまでと同様に株価上昇期待だけを煽ることはできなくなりつつあるのだ。配当や自社株買いはもとより、資本注入の必要性すらあるかもしれない。IMFの指摘するように、株価は実勢を反映していない。これから取るべきポジションも、その点に注意を払っておかないといけないだろう。
日本時間 15時30分
| 【2026年2月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年2月2日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!


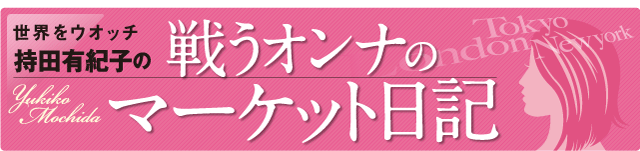
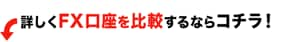
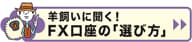



















![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)








株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)