昨日はアジア時間でリスク回避の流れが強まった。そもそも前日の米国株の軟調さの地合いを引き継いだ直後でもあり、そこへ持ってきて香港でもキャピタルゲイン課税の強化が図られることとなった。中国株はスローダウン。そして日本株も引きつられて大幅安になった。
そうしたリスクオフの状況からドル円は105円台の前半をウロウロしていたのだが、欧州時間に入ってからは急速に市場のリスク許容度が回復。特にユーロ円の上げ方がすごかった。欧米ではワクチンの接種ペースが早まるとの観測が強まって、それがリスクテークへと赴かせたのだ。ドル円も106円台に乗せてきたりしている。
パウエル議長の発言は前日と同じもの。ニューヨーク序盤で10年ものの利回りが1.43%台まで上昇したが、議長のトークの後で急速に低下した。
ところで長期金利というが、これは短期金利に対する便利な用語であって、実際には長期債の利回りをもって長期金利と呼んでいるだけだ。長期金利が2%だからといって、これは流通利回りであって、格別に2%分のお利息がもらえるわけではない。したがって厳密には長期金利と呼ぶには注意を要する。
株式運用などでも投資の運用利回りといった表現がなされる。また配当率を見ていくときにも配当利回りなどと言っている。利回りはあくまでも便宜的な尺度の一つであって、利息を表すための金利とは別物と思ってかからないといけないのである。
長期金利が上がると、その通貨の価値はどうなるのか。金利と同じようなものと混同していると、「長期金利の上昇は通貨高をもたらす」などといったコメントを行うことになる。これで間違っている評論家も多い。長期金利は金利ではなくインフレ、すなわち通貨価値の減退の度合いだと考えるのが順当である。
1980年代を通じて90年代の初旬までアメリカはインフレに悩まされ、長期金利は10%を遙かに超えていた。その際にドルはどうだったか。通貨価値の減少は避けられず、大幅なドル相場の全面安を招いたのである。
インフレが物価高と同等だということではない。しかし通貨価値の減退がインフレなのだから、表面化する現象として物価高も関係がないとは言えない。近いところではリーマンショックの直前まで、物価高が続いた。原油価格は150ドル近くまで上昇し、金価格も高騰。その時期にユーロドルは1.6台まで上がっており、ドル安も極まっていたのである。
FRBなど金融当局はインフレの進行を認めていない。あくまでもコロナ後の反動であり、一時的な物価高であるとしている。しかしそれは期待というか思惑であって、それを実体に即して正直に表すのはマーケットであろう。
とくに米債の先物価格の下げには注意を払わないといけない。何もなければ、それでよし。しかし後から振り返って「あれがインフレの始まりだったんだなあ」と後悔しないためにも、長期金利の動向には気を抜けない。場合によってはドルの全面安、しかも大幅安が待っているかもしれないのだ。
日本時間 15時00分
| 【2026年2月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年2月2日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!

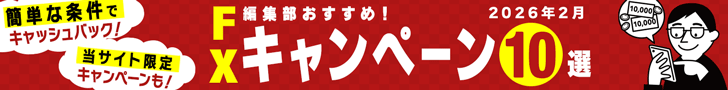
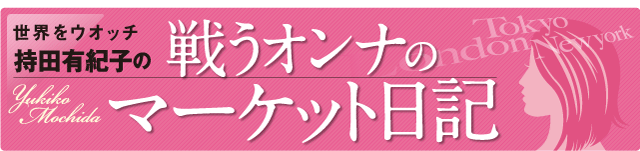
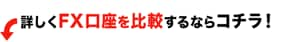
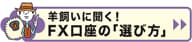


















![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)
![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)








株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)