(「YEN蔵さんに聞く為替ディーラーの世界(2) 凄まじき仲値の攻防。米屋が出てるぞ~!?」からつづく)
銀行の為替取引というと、顧客から手数料をとって堅実に儲けるというイメージもあるのだが、YEN蔵さんの話を聞くと、それだけではないようだ。
■200本売られたら、さらに上乗せして売る!
「個人顧客を相手にした外貨両替や外貨預金では、1ドルあたり1円とか2円といった手数料をとりますね。また、企業を相手にする場合でもセールスは手数料をとります(「セールス」については「YEN蔵さんに聞く為替ディーラーの世界(1) 白熱の毎日! 1日50回は「机に蹴り」!?」参照)。
けれど、インターバンクディーラーには手数料が落ちないんです。顧客の玉をさばいていく中で利益を上げていかないといけない。時にはやられちゃうこともありますよ。
たとえば、どこかの生保(生命保険会社)がシティバンクにドル/円を200本売ってきて、自分はそれをさばく立場だとしましょう。
そういう時は、往々にしてシティバンクだけじゃなくて、他の銀行にも次々と売っていたりするものなんですよ。そうすると、マーケットが一気に50銭ぐらいダーッと下がってしまいます。
それを単純にさばくだけだと、損になるんですが、そういう時は200本だけじゃなくて、自分で上乗せして、300本とか400本とか売るんです。それでマーケットがさらに下がれば、その部分で損を取り返して儲かるといったことになります。
もちろん、そうする際にはしっかりした自分の相場観を持ち、情報を総合的に判断することが必要になりますが…」

■ヘッジファンドが作り出す流れに真っ先に乗る!
先にインターバンクディーラーとプロップディーラーは分かれていると書いたが、YEN蔵さんのこういった話を聞いていくと、それらは単純に分けられるものでもないことがわかる。
「生保も結構、お行儀が悪くて、さっき言ったようなやり方で、一斉にたくさんの銀行に注文を出して、売り崩すようなことをするんですが、ヘッジファンドの玉もすごかったですね。たとえば、ジョージ・ソロスの『クォンタムファンド』みたいな大規模なヘッジファンドが攻めてくると、相場が大きく動きます。
大規模なヘッジファンドでは、ドル/円で1兆円とか2兆円とか、一方向に大きくポジションを傾けてくるところもありましたね。そういう玉をインターバンクディーラーとしては、いち早く取りたいんです。
真っ先にそういう注文が来れば、さばきやすいし、そのヘッジファンドが作り出す相場の流れにいち早く乗ることができます。自分もそれに乗っかってポジションを作れば、さらに儲かるというわけです。
だから、銀行は『いいサービスするから、真っ先にボクに売ってよ』といった話を有力なヘッジファンドにするんですよ。大きな銀行の利点としては、そういった有力投機筋のフローが見えやすいということがありましたね」
■3時間でドル/円が10円下がったスゴい相場とは?
ところで、ここ数カ月はあまり大きく動いていないドル/円相場だが、昨年の秋頃は1日で約7円と、短期間に急落したこともあった(「記事を書いているうちにみるみる下がっていくドル/円。いったいどこまで行くんだ~?」参照)。
約20年ほどのディーラー歴の中で、YEN蔵さんがこれまで経験してきたスゴい相場とはどんなものだったのだろうか?
「私が経験した相場で、短時間に一番大きく動いたのは1998年10月のドル/円相場ですね。この時はニューヨーク市場の3時間ほどでドル/円が10円下がったんですよ」
今の状況と似ている部分もある——として取り上げられることもある1998年の金融危機。この時は、1998年8月にロシア危機(ロシア国債のデフォルト=債務不履行)が起こり、その影響で、9月にアメリカの有力ヘッジファンド・LTCM(ロング・ターム・キャピタル・マネジメント)が破綻した。
そして、10月に入り、LTCM破綻の影響が金融市場を襲い、ドル/円も暴落した——と言われている。そのため、この時の相場はよく「LTCMショック」と形容されるのだが…。
「ドル/円が暴落した直接の原因はLTCMではなく、タイガーファンドだとマーケットではウワサされていました」
「タイガーファンドはジュリアン・ロバートソンがやっていたヘッジファンドで、ジョージ・ソロスのクォンタムファンドと同じぐらいか、それよりも規模の大きい有名なファンドだったんです。
この時、タイガーファンドはドル/円のロングポジション(買い建て玉)をすごくたくさん持っていたようです。その量は一説には数万本とも言われていました。
このタイガーファンドが“飛んで”しまって、数万本のドル/円ロングポジションがどうやら一気に投げられてしまったようなのです。それでマーケットがクラッシュしました」
この時、タイガーファンドはドル/円のロングポジション(買い建て玉)をすごくたくさん持っていたようです。その量は一説には数万本とも言われていました。
このタイガーファンドが“飛んで”しまって、数万本のドル/円ロングポジションがどうやら一気に投げられてしまったようなのです。それでマーケットがクラッシュしました」
■レートの大台がわからなくなってしまった
ドル/円が3時間で10円下がるような相場では、ディーリングルームはどんな修羅場になるのだろうか?
「その日、私は運悪く遅くまで残っていましてね。東京はもう夜。ニューヨーク市場に入っている時間でも、セールスからドンドン売ってくださいと注文が入るんです。
もうね、レートの大台がわからないんですよ。さっき売ったのは123円台だったか、122円台だったか…。1円刻みで落ちていくんですから。
その頃はもうEBSが普及していて自動的に記録が残りますからまだ良かったのですが、人が電話でやりとりしていた時代だったら、ホントに取引内容がわからなくなっていたかもしれないですね」(「EBS」については「YEN蔵さんに聞く為替ディーラーの世界(2) 凄まじき仲値の攻防。米屋が出てるぞ~!?」参照)
■暴落相場で実はディーラーは儲かる!?
「休むも相場」という言葉がある。個人トレーダーの場合、あまりにも難しい相場だったら、手を出さないで見ているというのも一つの立派なやり方だ。根本的な疑問になるが、銀行の場合は、やはり、「注文を拒否して見ているだけ」ということはできないのだろうか?
「いえ、拒否しようと思えばできるんですが、『巨人軍は紳士たれ』じゃないけど、シティバンクはいつでもプライスを出す! 絶対逃げちゃダメ! みたいなプライドを持っていたんですよ。
でも、実はこういう激しい相場では、プライスを出し続けると儲かるんです」

「そんな場合は、通常時のように売値と買値を2ウェイで提示するのはムリ。まず、『売るのか、買うのか、どちらのサイドか言ってください』と相手方に伝えます。もう、みんな、売り、売り、売りですから、買ってくれたらラッキーぐらいの感覚ですけどね。
そして、レートも余裕を持って提示します。
たとえば、マーケットで最後に出合ったのが(約定したのが)123円だとしますよね。こういう暴落相場では、その時点で、マーケットにある買い指値はもう122円ちょうどぐらいになったりしています。そこで、さらに低く、『今だと121円でしか売れませんよ』と伝えます。
そうやって、1円ぐらいの余裕をみておけば、さらに122円から、みるみる相場が下がっていったとしても、その下落過程でなんとか全注文をさばいて、利益を出せることもあるわけです。
もちろん、提示するレートは注文の量や相場の動きによって、変化させる必要があります。その時、どんなふうにレートを出していくのかは、ディーラーの感覚と読みが問われるところですね。
でも、そんな暴落相場では、とにかくレートを出し続けていれば、どんなにひどいレートでもお客さんに『どうもありがとう』と感謝されるものなんですよ。そして、こちらは結構儲かったりするんです。大変なのは確かですが…」
(「YEN蔵さんに聞く為替ディーラーの世界(4) なぜ、豪ドルが一番おすすめなのか?」へつづく)
(取材・文/ザイFX!編集部・井口稔 撮影/和田佳久)
| 【2026年2月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年2月2日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!


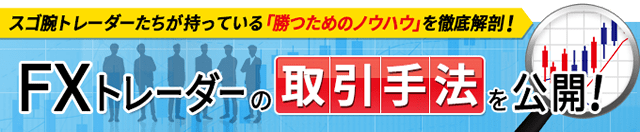
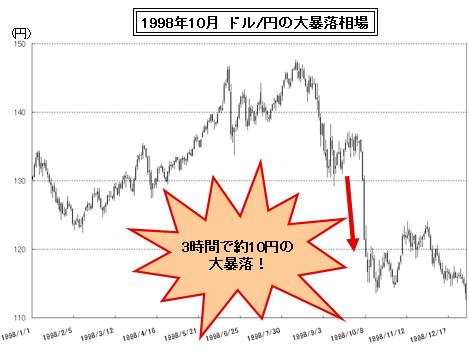
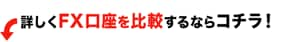
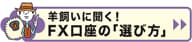


















![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)








株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)