先週末はついにドル円が歴史的な安値を更新した。といってもあまり破壊力のあるものではなかった。そこまで連日のように76円台でのスタックが続いていただけに、いつドル円が75円台に差しかかっても驚かないというような雰囲気が醸し出されていたのもあるのだと思う。
テクニカル面を重視した比較的にコストの低いところで作ったロングポジションの投げ売りがいっせいに出て、その力で75円台に突入はしたものの、短期筋などによる追随はなし。あえて75円台を拾うという向きも見られなかったが、事前に76円台に戻っていったという感じ。
あとは介入警戒感も徐々に出てきて、76円台の中盤まで押し戻されてしまった。日中の足型だけで見ると、上も下もやったという感じで、相変わらず値幅は小さいものが続く。
一方でユーロドルだが、これも方向感が定まらず、ここ3カ月間は1.41から1.44台までをコアレンジとしたもみ合いが続いている。1.40台まで行けば、そこは拾い場。また1.45台に乗せてくれば、そこで売り込むのがよいだろうという、レンジ相場を形成している。欧州の信用不安の高まりや、米国株の急落などによるリスク許容度の減退でも、レンジブレークしないということの意味は大きい。
今晩はほとんど経済指標らしきものはない。しかし今週いっぱいを見渡すと、いろいろと注目されるべきイベントが立ち並んでいる。まずは日本の金融当局の出方である。円相場が75円台を見た後である。いくら代表選挙で忙しいといても、一つの国難であることは間違いない。手をこまねいている場合ではなさそうだ。
「レベルを選んで介入しているわけではない」と言い切っているのだから、いつマーケットに出てくるのかも懐疑的になりつつある。それではタイミングかというと、当局が心配している「過度な変動」は起こっておらず、毎日、狭いレンジでの往ったり来たりが繰り返されているだけだ。仮に介入をしたところで、その後のフォローアップはあるのかないのかなど、市場との対話が十分でないことがうかがわれる。
ちなみに前回の、すなわち今月第一週の介入では、確かにドル円は80台を回復したが、本来の目的である景気浮揚、つまるところ株価の上昇を指そうと言う意味においては、日経先物などは100円しか上がらなかったので、まずは失敗だったといえるだろう。
野田大臣などが「効果のある」と強調しているのは、ここの部分を指しているのだろう。しかし効果的にやるとなると、相当の困難がともないそうだ。現状の株安は円相場だけで解決される問題ではないからだ。
次に週末にバーナンキ議長のスピーチがひかえている。昨年と同じでジャクソンホールで行われ、前回のここでの指摘でQE2が始まったことが連想されて、たいへんな関心を集めている。今年も何かあるのではないか、と。それがQE3の端緒になるのではないかという憶測が飛んでいる。
しかし現実を考えると、金融緩和へのハードルは高そうだ。食料品をはじめとして、世界にインフレをバラまいたとの避難もあり、政治的な側面からQE3は困難のように見える。それでもマーケットは何か刺激策の一環のようなものがうちだされるのではないかと期待しているようだ。いまだにFRB神話のようなものが生きているのかもしれないが…。
日本時間 18時20分
| 【2025年12月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2025年12月1日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!

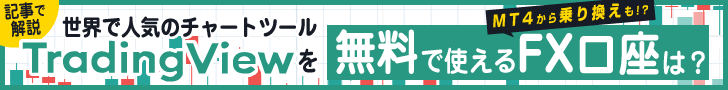
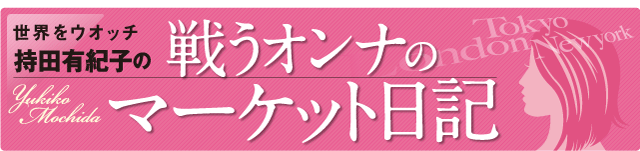
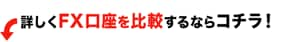
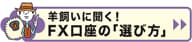


















![ヒロセ通商[LION FX]](https://zaifx.ismcdn.jp/mwimgs/c/f/-/img_cf441770d8ee58a063c99fd812f7fc7a76045.gif)
![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](/mwimgs/c/d/-/img_cd98e6e3c5536d82df488524d85d929d47416.gif)








株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)