米企業の決算発表が本格化してきた。経済指標などマーケットすべてに影響を与えるデータをマクロ指標という一方で、企業決算はミクロ指標という。ミクロ指標であっても市場の反応は同じようなものであり、やはり事前予想と実際の結果との比較になる。
何を予想するのかというと、株価関連の場合は企業利益を見るのである。利益の絶対額を論じる場合もあれば、1株あたりに引き直したもので見る場合もある。前者は日本で多くが見られ、アメリカや欧州では後者で測る。
企業利益の大きさを利益の絶対額で比較しても、1株あたり利益(=EPS)で比較しても同じことである。EPSは時価総額を株式数で割っただけだからだ。だから株価がそもそも高い企業のEPSは大きなEPSとなることになる。EPSが大きいからといって素直に喜べる性質のものではない。
あくまでも事前予想のEPSと、結果のEPSを比べるのだ。ちなみに株価をEPSで割ったものをPERという。これは企業利益の何年分を積み重ねれば、出資分をすべて回収できるのかを示すものである。EPSが高ければPERは低下し、その株価は割安だという解釈になる。
そういうわけで昨日のニューヨーク序盤では、米企業決算が相次いだ。GSやシティ銀、ウェルズファーゴといった金融大手は押しなべて予想に従う決算結果だった。
またユナイテッド・ヘルスやJ&Jなどの化学分野の決算はアナリスト予想を大いに上回ったので、マーケットは全体的にリスクテーク寄りの姿勢となった。前日に米国株が程よく価格調整をしていたので、買いやすかったという一面もあったのだろう。
ドル円も108円台のミドルから108円台の後半まで上昇。これまでは108円台の中盤以降はかなりのオファーがあるとされていたのだが、実際にそこまで到達してみると存外に上値は軽かった。私としては108円台の後半の見えているオファーが気になる分だけ、ここからは買い上がってはいけないという思いが強い。
一方でイギリスがEU側と合意できそうな可能性も出てきたという見方が出てきた。どれを根拠にしているのかわからないが、妙に楽観的なのである。これで明日からのEU首脳会議も乗り切れるといったようなムードである。それに伴ってポンドも一段高。本当に合意なき離脱が回避できるのならば、ポンドドルは1.30台まで戻してもおかしくはないところなのだが。
日本時間 15時00分
| 【2026年2月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年2月2日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!


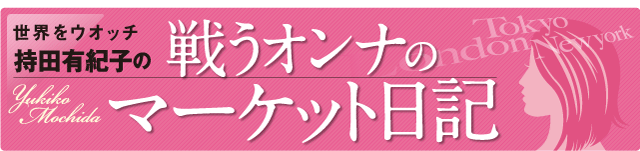
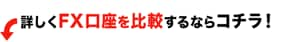
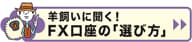




















![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)







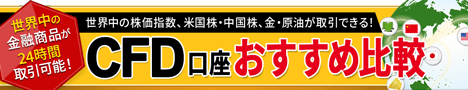
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)