■米ドル/円の史上最安値更新もささやかれているが…
足元の為替市場では、米ドル全面安の状況が続いている。円を含め、各主要通貨に対する米ドル安の勢いが止まらないようにも見える。
当然のように、マスコミの論調と市場コンセンサスはトレンドの後を追う形で米ドル安に傾いてきた。つい2カ月前まではユーロ崩壊を心配していたが、最近は米ドル安進行への不安に集中している(「ドル安が進んでからドル安の材料探し。専門家の話は所詮トレンドの後追いだ!」を参照)。
特に、米ドル/円は一時85円割れ目前まで「円高・米ドル安」が進み、昨年11月安値の84.80円をうかがう水準まで一気に下落してきたため、1995年につけた最安値の80円をもトライするのではないかといった懸念が強まっている。
この件については、つい最近GDP予測を修正した日銀、さらに、国際協調をアピールし、中国に人民元切り上げを要求している日本政府がともに市場介入に踏み切れないため、より現実的に見えてしまう。
米ドル/円 日足
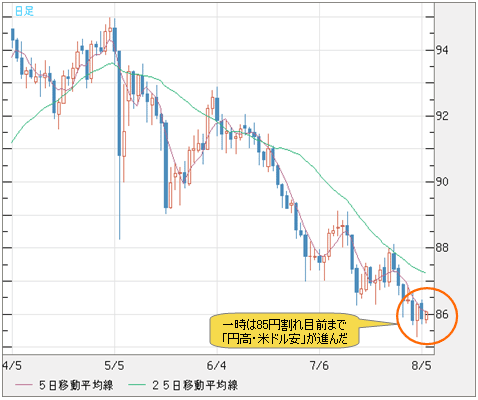
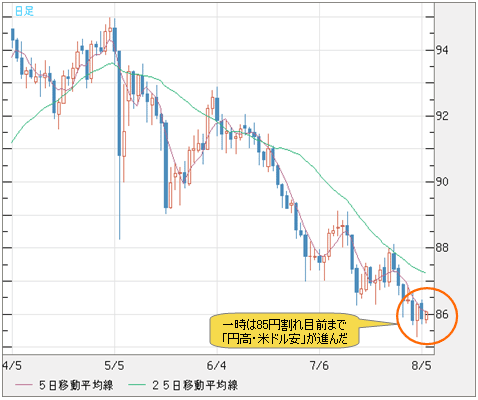
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足)
筆者は、自身が発行しているレポートにおいて、かなり前からこのことを指摘していた。すなわち、「ドルインデックスは今年後半に暴落する可能性があり、米国サイドの何らかのサプライズに警戒」というものだ。
したがって、筆者にとってはサプライズではまったくない。だが、一部の市場参加者にとってはサプライズであったため、これが米ドル安進行を後押ししたように見える。
それは他ならぬ、米国の量的緩和策の再開である。
■米国の「失われる十年」は始まったばかり
ユーロ圏の国々のソブリンリスク(国家に対する信用リスク)がマスコミなどで大げさに取り上げられる中、フタを開けてみれば、総じてユーロ圏のほうが経済指標は堅調で、米国サイドは不調なものが目立つ。
最近の芳しくない経済指標の結果を受け、米FRB(連邦準備制度理事会)のバーナンキ議長らが弱気発言を連発し、市場参加者の肝を冷やした。日本時間今夜に発表される7月の米国雇用統計を皆が固ずを呑んで見守り、弱い結果となれば、さらに米ドル売りへと傾くだろう。
もっとも、このような事態が筆者にとってまったくサプライズでないということは、このコラムを読み続けてきた読者のみなさんなら、おわかりいただけるはずだ。
米国は日本の二の舞となり、「失われる十年」が始まったばかりなので、本当の苦難はこれからだ。
そもそも、「ヘリコプター・ベン」というニックネームを持つ人物のFRB議長就任は、このような局面に対応させるための人事であって、バーナンキ氏が躊躇することなく量的緩和策を再開しても何の不思議もない。
■「ドルキャリートレード」が現実のものになる!
8月6日(金)に結果が発表となる米国雇用統計の良し悪しが短期スパンの値動きを左右するとしても、中長期スパンでは、米国の量的緩和策の再開は必至だ。
筆者は、自身が発行しているレポートにおいて、かなり前からこのことを指摘していた。すなわち、「ドルインデックスは今年後半に暴落する可能性があり、米国サイドの何らかのサプライズに警戒」というものだ。
したがって、筆者にとってはサプライズではまったくない。だが、一部の市場参加者にとってはサプライズであったため、これが米ドル安進行を後押ししたように見える。
それは他ならぬ、米国の量的緩和策の再開である。
■米国の「失われる十年」は始まったばかり
ユーロ圏の国々のソブリンリスク(国家に対する信用リスク)がマスコミなどで大げさに取り上げられる中、フタを開けてみれば、総じてユーロ圏のほうが経済指標は堅調で、米国サイドは不調なものが目立つ。
最近の芳しくない経済指標の結果を受け、米FRB(連邦準備制度理事会)のバーナンキ議長らが弱気発言を連発し、市場参加者の肝を冷やした。日本時間今夜に発表される7月の米国雇用統計を皆が固ずを呑んで見守り、弱い結果となれば、さらに米ドル売りへと傾くだろう。
もっとも、このような事態が筆者にとってまったくサプライズでないということは、このコラムを読み続けてきた読者のみなさんなら、おわかりいただけるはずだ。
米国は日本の二の舞となり、「失われる十年」が始まったばかりなので、本当の苦難はこれからだ。
そもそも、「ヘリコプター・ベン」というニックネームを持つ人物のFRB議長就任は、このような局面に対応させるための人事であって、バーナンキ氏が躊躇することなく量的緩和策を再開しても何の不思議もない。
■「ドルキャリートレード」が現実のものになる!
8月6日(金)に結果が発表となる米国雇用統計の良し悪しが短期スパンの値動きを左右するとしても、中長期スパンでは、米国の量的緩和策の再開は必至だ。
米国の雇用指標

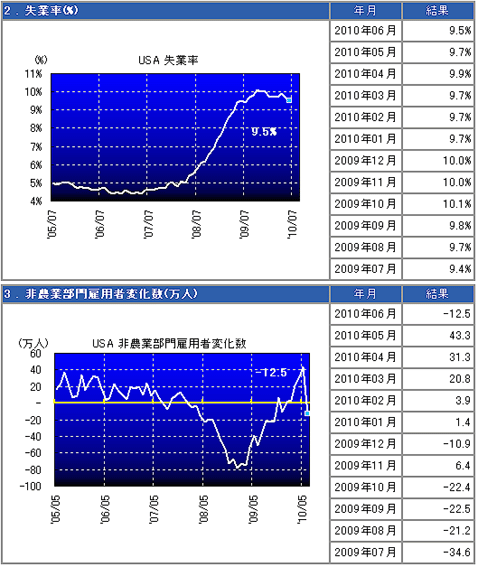
(詳しくはこちら → 経済指標/金利:米国主要経済指標の推移)
これから、多くの読者のみなさんが覚えのある1つの言葉が現実となるだろう。それは「ドルキャリートレード」である。
「実質ゼロ金利」である米国サイドの量的緩和(具体的な方法はともかく、本質的に米ドルを刷ってばらまくことを意味する)は、昨年とは異なり、今度こそ本物の「ドルキャリートレード」をもたらす。
筆者は昨年末に「ドルキャリートレード」という言葉が幻になると指摘したが、その後のギリシャ危機の発生によって「ドルキャリートレード」自体が死語となった。
そして、ユーロ圏のソブリンリスクの危機がこれから必然的に米国に飛び火するにつれ、その「ドルキャリートレード」という死語は復活し、本質を物語ることになるだろう。
■「ドルキャリー」の流行で、米ドル/円は上昇する
このあたりの考え方や論理の解釈については次回以降に譲るとして、今回のコラムでは、「ドルキャリートレード」が流行すると、米ドル/円相場にどのような影響があるのかを詳しくご説明したい。
結論を先に言うならば…
これから、多くの読者のみなさんが覚えのある1つの言葉が現実となるだろう。それは「ドルキャリートレード」である。
「実質ゼロ金利」である米国サイドの量的緩和(具体的な方法はともかく、本質的に米ドルを刷ってばらまくことを意味する)は、昨年とは異なり、今度こそ本物の「ドルキャリートレード」をもたらす。
筆者は昨年末に「ドルキャリートレード」という言葉が幻になると指摘したが、その後のギリシャ危機の発生によって「ドルキャリートレード」自体が死語となった。
そして、ユーロ圏のソブリンリスクの危機がこれから必然的に米国に飛び火するにつれ、その「ドルキャリートレード」という死語は復活し、本質を物語ることになるだろう。
■「ドルキャリー」の流行で、米ドル/円は上昇する
このあたりの考え方や論理の解釈については次回以降に譲るとして、今回のコラムでは、「ドルキャリートレード」が流行すると、米ドル/円相場にどのような影響があるのかを詳しくご説明したい。
結論を先に言うならば…
もし「ドルキャリートレード」が流行すれば、豪ドルや加ドルといった高金利通貨がもっとも恩恵を受け、その次に、ユーロや英ポンドなど構造的問題を抱える通貨に恩恵があると思われる。
半面、円はもっとも恩恵を受けにくい通貨となるだろう。理屈は簡単で、円は米ドル以上に「実質ゼロ金利」の通貨だからだ。
この前提をもとにして推測すれば、「ドルキャリートレード」の流行は、米ドル/円にとってはむしろプラス(上昇圧力)である。
その理由は次のとおりだ。
半面、円はもっとも恩恵を受けにくい通貨となるだろう。理屈は簡単で、円は米ドル以上に「実質ゼロ金利」の通貨だからだ。
この前提をもとにして推測すれば、「ドルキャリートレード」の流行は、米ドル/円にとってはむしろプラス(上昇圧力)である。
その理由は次のとおりだ。
豪ドル/米ドル 日足

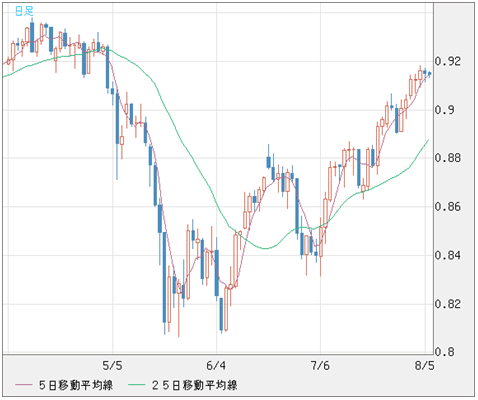
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:豪ドル/米ドル 日足)
たとえば、豪ドル/米ドルの上昇スピードが速ければ速いほど、豪ドル/円においても上昇傾向がもたらされる。そして、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)相場で円安圧力がかかれば、それが米ドル/円にも波及して、結果、米ドル/円は連れ高するということだ。
■7月分の米国雇用統計は懸念されるほど悪くない!?
それでは、中長期スパンの話ではなく、短期スパンではどうなるかを考えてみよう。
「ファンダメンタルズはいつも、トレンドの後を追って展開するもの」という「私流」の考え方に沿ったロジックをもとにすれば、筆者は、日本時間今夜に発表となる米国の雇用統計が、多くの市場関係者が懸念しているほど悪くないのではないかと思っている。
なぜなら、米ドル安のスピードが速すぎて、そろそろ一服してもおかしくない段階に来ているためだ。ファンダメンタルズの何らかの材料が、そろそろ出てきても不思議はない。
この意味で、米ドル/円の下げ余地には限度があると思う。
米国雇用統計の結果が悪ければ、昨年11月安値の84円台後半を割り込んでもおかしくはない。だが、1995年安値の79円台に迫るほどの円高のモメンタムはないだろう。
テクニカル・アナリシスの視点では、このコラムでもたびたび指摘してきたように、2005年1月安値を起点とした「5年サイクル」が昨年11月安値で完了したのかどうかが焦点になる(「5年サイクルで見て今は円安トレンド。人民元弾力化による円高進行は続かない」を参照)。
仮に、昨年11月安値で完了せず、今年に延長されたとしても、日柄的にはそろそろ底を迎えてもおかしくはない。
■「リスク・リバーサル」で米ドル/円相場を見ると…
その上、前回のコラムで書いたように、オプション売買絡みで見る指標の1つも米ドル/円の底打ちを示唆している。その指標は「リスク・リバーサル」だ。
オプションは、プロの市場参加者を中心に取引される金融商品であるだけに、通貨オプション市場における「リスク・リバーサル指数」は彼らの思惑を反映するものとされている。
「リスク・リバーサル指数」は為替レートと同じく日々変化するから、その高安は、プロの市場参加者がこの通貨がどちらに動く可能性が高いと見ているかを見る目安となる。
具体的な説明は省くが、要するに「リスク・リバーサル指数」と「スポットレート」のカイ離に注目すれば、良い取引チャンスがつかめるのだ。
「スポットレート」と「リスク・リバーサル指数」のカイ離が大きければ大きいほど、スポットレートがこれから、リスク・リバーサル指標の方向に歩み寄る可能性が高いということだ。
■米ドル/円もこのあたりで反発上昇か?
筆者の手持ちのツールに「スポットレート」と「リスク・リバーサル指数」を表示するチャートがないため、ここでお見せできないのは残念だ。
だが、ここでは、6月以降、ユーロ/米ドルの「リスク・リバーサル指数」と「スポットレート」のカイ離の拡大に注目し、ユーロの「コールポジション(※)」に食指を伸ばしたことをご紹介しておく。
(編集部注:「コール」は買う権利のことで、「プット」が売る権利のこと)
たとえば、豪ドル/米ドルの上昇スピードが速ければ速いほど、豪ドル/円においても上昇傾向がもたらされる。そして、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)相場で円安圧力がかかれば、それが米ドル/円にも波及して、結果、米ドル/円は連れ高するということだ。
■7月分の米国雇用統計は懸念されるほど悪くない!?
それでは、中長期スパンの話ではなく、短期スパンではどうなるかを考えてみよう。
「ファンダメンタルズはいつも、トレンドの後を追って展開するもの」という「私流」の考え方に沿ったロジックをもとにすれば、筆者は、日本時間今夜に発表となる米国の雇用統計が、多くの市場関係者が懸念しているほど悪くないのではないかと思っている。
なぜなら、米ドル安のスピードが速すぎて、そろそろ一服してもおかしくない段階に来ているためだ。ファンダメンタルズの何らかの材料が、そろそろ出てきても不思議はない。
この意味で、米ドル/円の下げ余地には限度があると思う。
米国雇用統計の結果が悪ければ、昨年11月安値の84円台後半を割り込んでもおかしくはない。だが、1995年安値の79円台に迫るほどの円高のモメンタムはないだろう。
テクニカル・アナリシスの視点では、このコラムでもたびたび指摘してきたように、2005年1月安値を起点とした「5年サイクル」が昨年11月安値で完了したのかどうかが焦点になる(「5年サイクルで見て今は円安トレンド。人民元弾力化による円高進行は続かない」を参照)。
仮に、昨年11月安値で完了せず、今年に延長されたとしても、日柄的にはそろそろ底を迎えてもおかしくはない。
■「リスク・リバーサル」で米ドル/円相場を見ると…
その上、前回のコラムで書いたように、オプション売買絡みで見る指標の1つも米ドル/円の底打ちを示唆している。その指標は「リスク・リバーサル」だ。
オプションは、プロの市場参加者を中心に取引される金融商品であるだけに、通貨オプション市場における「リスク・リバーサル指数」は彼らの思惑を反映するものとされている。
「リスク・リバーサル指数」は為替レートと同じく日々変化するから、その高安は、プロの市場参加者がこの通貨がどちらに動く可能性が高いと見ているかを見る目安となる。
具体的な説明は省くが、要するに「リスク・リバーサル指数」と「スポットレート」のカイ離に注目すれば、良い取引チャンスがつかめるのだ。
「スポットレート」と「リスク・リバーサル指数」のカイ離が大きければ大きいほど、スポットレートがこれから、リスク・リバーサル指標の方向に歩み寄る可能性が高いということだ。
■米ドル/円もこのあたりで反発上昇か?
筆者の手持ちのツールに「スポットレート」と「リスク・リバーサル指数」を表示するチャートがないため、ここでお見せできないのは残念だ。
だが、ここでは、6月以降、ユーロ/米ドルの「リスク・リバーサル指数」と「スポットレート」のカイ離の拡大に注目し、ユーロの「コールポジション(※)」に食指を伸ばしたことをご紹介しておく。
(編集部注:「コール」は買う権利のことで、「プット」が売る権利のこと)
ユーロ/米ドル 日足

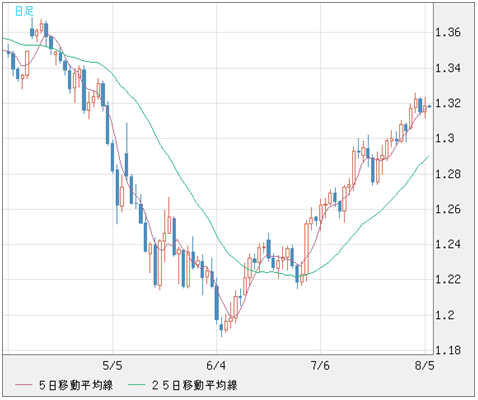
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 日足)
その後、ユーロが大幅に切り返したために、そのカイ離はかなり解消された。
ところが解消されていない通貨もあって、その代表が米ドル/円である。
6月以降のユーロ/米ドルほどではないが、米ドル/円におけるカイ離は一貫して保たれてきただけに、そろそろ修正されてもよいだろうと見ている。
もちろん、米ドル/円のレートは、下がるよりも上がるほうが確率的には高い。
何? 君は円のプットオプションを買ったかって? それはご想像におまかせ!
(2010年8月6日 13時20分記述)
その後、ユーロが大幅に切り返したために、そのカイ離はかなり解消された。
ところが解消されていない通貨もあって、その代表が米ドル/円である。
6月以降のユーロ/米ドルほどではないが、米ドル/円におけるカイ離は一貫して保たれてきただけに、そろそろ修正されてもよいだろうと見ている。
もちろん、米ドル/円のレートは、下がるよりも上がるほうが確率的には高い。
何? 君は円のプットオプションを買ったかって? それはご想像におまかせ!
(2010年8月6日 13時20分記述)

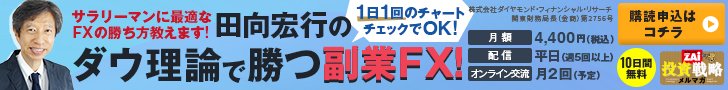











![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)









株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)