昨日の海外相場では、株価が多少の反転を示した。まあ、大きな下げの後の自律反発といったところだろう。株価上昇のきっかけになったのは、イタリアの短期債の入札であった。いつものパターンで入札が無事に終了すれば、それで資金繰りは何とかなったということで、安心感からユーロが買われて、次いでリスクテークに進むというものだ。私はユーロドルの1.35台や1.36台ではとてもブルになれず、欧州時間ではまったく手が出なかった。どうせならばニューヨーク市場まで待ってみようという感じだ。
しかし欧州の情勢はかなり厳しそうだ。無事に通過したということで反発のきっかけになったイタリアの1年ものの短期債だが、落札された利回りが6.087%であった。ECBが前回に利下げを行ったなかで6%越えをいうのもすごいが、前回の入札の時は3%台であったことと比較すると、その上昇の激しさは一目瞭然だ。単に入札が済んだからといって、そこからリスクテークに励んでいってもよいという情勢にはないというのも明らかだと思う。
そもそもまだユーロドルをショートにしたくなる理由は山ほどもある。まずは直近のECBのアクションだが、インフレの傾向が見えないことを理由にしているが、なんといっても景気重視型の利下げであったことは言うまでもない。ユーロ圏は大幅に来年度の成長率も下方修正している。ともかくこれで当面の利上げ期待は完全に払しょくされてしまい、金利の方面からはユーロの買いの魅力は減退した。
第二に日銀のドル買い介入である。これは直接にはユーロドルには介在していないが、マーケットからドルがその分だけ吸い上げられたことには変わりがない。そのドル不足が回りまわってユーロドルにも間接的な影響を与えていると言わねばならない。これは介入のあった当日にいきなりユーロドルが下落を始めたことからも確かめられる。
そしてテクニカル面だ。10月31日の介入以降のユーロドルの下げはすでに700ポイント以上に及んでおり、この間に買ってしまった、もしくは買わされてしまったポジションの整理は一朝一夕にはいかないだろう。たとえそれがオプションのようなデルタヘッジの場合でも同様で、次回に相場がラリーしていっても、目先の相場を重くする要因になることには変わりがない。
そして最後にユーロが安くなると、どうしてもクロス円も下落してしまう、マーケット全体がリスク回避に向かうということである。株安が進めば、その分だけさらにユーロ売りを誘ってしまう形となる。
そういうわけでユーロの戻りを期待してニューヨーク相場を迎えたのだが、欧州の信用不安が薄くなったということを材料にリスクテークが進んで、株高とユーロ買いが進んでいった。ユーロドルも1.36台のミドルまで上がってきたが、まだ身体が夏時間モードになっているせいか、とても眠い。ポジションを作れずに翌朝を迎えてしまった。ユーロドルは1.35台に逆戻りしていた。
本日はアジア時間でややリスクテーク気味だった。グローベックスでは米国株が昨日の高値を上抜いてきたことで、ユーロドルも上昇。1.36台に再び乗せてきて高値追いの態勢に入っている。今晩はミシガン大学くらいしか経済指標はないが、欧州からのニュースに気をつけねばならないのは同じだ。
ニュースには即時に触れることは困難なので、出来ることといったら為替レートのウォッチだけである。妙な値動きがあったら、とりあえず同じ方向で攻めてみることだ。特に私の場合はユーロベアなので、下げ方向のプライスアクションには敏感になっている。
日本時間 19時00分
| 【2026年1月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年1月5日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!

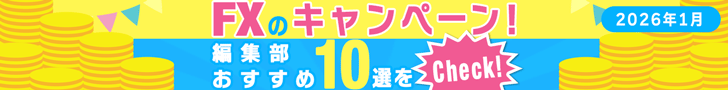
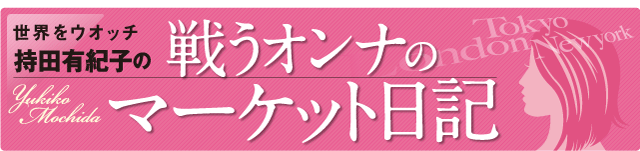
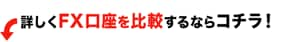
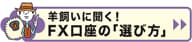


























株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)