先週の金曜日はクリスマスのため世界中がお休みだった。そのためマーケットもやっておらず、金融相場も動いていない。そして今週は年末に向かってますますマーケットは閑散としてくることが予想される。
ところで日経平均株価はだいたい28000円台の中盤をやっているが、日経先物の中心限月である3月限の取引価格はそれよりも50円ほど安い。これは12月末時点で支払われる配当分にあたる、いわゆるキャリイングコストだ。両者はパラレルに動いているので、価格差だけを問題にする限り、損益的には問題はない。
同じことを日経先物の3月限と6月限で見てみると、価格差は300円ほどもある。これは3月末の配当の権利落ち分である。日本企業の場合は3月末に配当を出す会社が多いので、この時期の権利落ちは大きいものとなる。
日経先物の12月限と3月限で300円も価格差があるというのは、そもそも株価が高いからというのが理由の第一である。配当というのは株価に対する比率で支払われるものだからである。株価が1万円のときと3万円の時とでは、3倍近くの差が出ても当然だろう。
またコロナ後の世界で企業利益が膨らんでいるのであれば、それは配当率そのものを押し上げることになる。株価の高さといい、企業利益の大きさといい、日経平均ベースでの配当分が300円というのは、まだまだ配当が少なすぎるようにも見える。
よく言われるように企業の内部留保がたまりすぎているというのは、貯金があって良さそうにも思えるのだが、企業活動として見る限り、それはROEを引き下げていることにつながる。会社内部に使わないお金が余っているならば、その企業の価値は現預金と同じであって、事業に配分されているリスクマネーたり得ないということだ。
投資家が期待するのは、預けたお金はすべて事業に使ってほしいということ。それをため込んだとあっては、失望を招く。100で買った株券が、半分は現金だったと言うことになれば、安全ではあるかも知れないが、値上がりの面などでの投資妙味に欠ける。欧米の企業ではお金を余らせないように、配当の増額をするとか、自社株買いを積極的に行っている。日本でも見られるのだが、規模はまだまだ小さいものにとどまっている。
米国株は大企業の自社株買いもあって、史上最高値に張り付いている。為替相場のほうも、そうした根強いリスクテークムードを受けてクロス円が強含みだ。とはいえまったく動きは少なく、本日はまだクリスマスモードが続くのだろう。だが閑散としたなかの不意な動きには気をつけてはおきたい。
日本時間 15時00分
| 【2026年2月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年2月2日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!


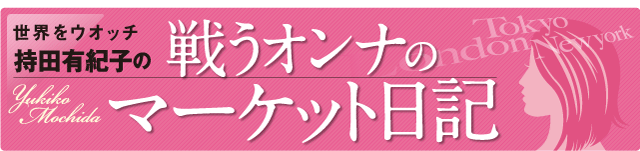
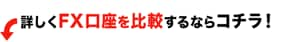
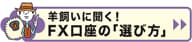


















![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)







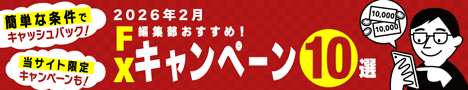
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)