為替マーケットは保ち合いの状況となっている。
ギリシャ問題やユーロ圏のソブリンリスクなどから、ユーロ安を懸念する声が強かったが、足もとではユーロ安は一服感が強く、むしろ英ポンドの軟調が目立つ。
3月1日(月)には、昨年の高値と比べ、英ポンド/米ドルは2270pips、英ポンド/円は3100pips(※)近くとなる下げ幅を一時記録した。
(※編集部注:「pips」とは取引レートの最小単位のこと)
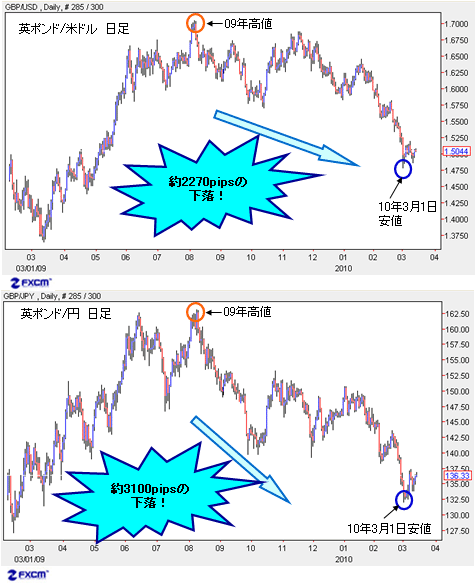
(出所:米国FXCM)
■「ギリシャ以下」と見なされている英ポンド
それだけではなく、英ポンドはユーロに対しても下げ幅を拡大している。それは、英ポンドがマーケットから「ギリシャ以下」と見なされていることを物語っている。
ギリシャ問題が飛び火し、英ポンド安が引き起されたという見方もあるが、筆者からみれば、それはまったくの誤りである。
英国のソブリンリスクはユーロ圏のソブリンリスクより深刻で、英ポンド安はギリシャ問題がなくても起こるべくして起こったものと受け止めている。
筆者がそう主張するのは、今さらの後解釈ではない。昨年10月と12月の本コラムでは、英ポンド安の進行に警鐘を鳴らし、「ポンドキャリートレード」が盛んになるリスクについて注意をうながしていた(「年末に向け、米ドルのリバウンドと英ポンドの『サプライズ』に備えるべき!」「そろそろ英ポンドのサプライズが起こる!? 来年は『ポンドキャリートレード』が流行か?」参照)。
目下のトレンドはまさにそのとおりの展開と言える。
■英ポンド安が進行した3つの理由
では、英ポンド安が「必然的」に進行した背景はどこにあるのか? まとめると、おおむね以下の3点が挙げられるだろう。
まず、英国の財政赤字はGDPに対する比率が12%に達しており、これからも拡大していく見通しだ。
同比率はギリシャ並みであるが、肝心なところは、英国の製造業にしても、銀行業にしても問題が山積みということ。
同時進行している貿易赤字は大幅な英ポンド安でも改善される気配がないようだ。実際、リーマンショック以来、英ポンドは25%も暴落していたが、1月貿易赤字は逆に17カ月ぶりの高い水準に膨らんでいた。
■「ギリシャ以下」と見なされている英ポンド
それだけではなく、英ポンドはユーロに対しても下げ幅を拡大している。それは、英ポンドがマーケットから「ギリシャ以下」と見なされていることを物語っている。
ギリシャ問題が飛び火し、英ポンド安が引き起されたという見方もあるが、筆者からみれば、それはまったくの誤りである。
英国のソブリンリスクはユーロ圏のソブリンリスクより深刻で、英ポンド安はギリシャ問題がなくても起こるべくして起こったものと受け止めている。
筆者がそう主張するのは、今さらの後解釈ではない。昨年10月と12月の本コラムでは、英ポンド安の進行に警鐘を鳴らし、「ポンドキャリートレード」が盛んになるリスクについて注意をうながしていた(「年末に向け、米ドルのリバウンドと英ポンドの『サプライズ』に備えるべき!」「そろそろ英ポンドのサプライズが起こる!? 来年は『ポンドキャリートレード』が流行か?」参照)。
目下のトレンドはまさにそのとおりの展開と言える。
■英ポンド安が進行した3つの理由
では、英ポンド安が「必然的」に進行した背景はどこにあるのか? まとめると、おおむね以下の3点が挙げられるだろう。
まず、英国の財政赤字はGDPに対する比率が12%に達しており、これからも拡大していく見通しだ。
同比率はギリシャ並みであるが、肝心なところは、英国の製造業にしても、銀行業にしても問題が山積みということ。
同時進行している貿易赤字は大幅な英ポンド安でも改善される気配がないようだ。実際、リーマンショック以来、英ポンドは25%も暴落していたが、1月貿易赤字は逆に17カ月ぶりの高い水準に膨らんでいた。
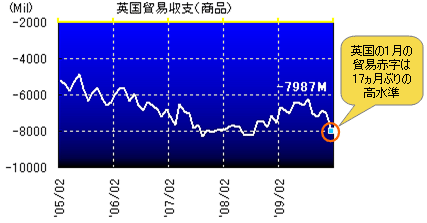
(詳しくはこちら → 経済指標/金利: 欧州主要経済指標の推移)
製造業が落ちこむ一方、稼ぎ頭だった銀行業も危機的な状況にある。業界全体が今後3~4年の間に7920億ドルの不良債権を処理しなければならないという研究報告があるほどだ。
■政局は混迷、金融政策は不透明な英国
次に、英政局の混迷だ。
現在与党の労働党と野党の保守党は5月の選挙でいずれも多数派にならないといった見通しがあり、政局の混迷が続けば、今後英国は財政赤字削減に取り組むどころか、財政赤字を逆に拡大させる恐れさえある。
このような不信感が広まるなか、英ポンドが買われる展開は想定しにくい。
最後に、もっとも決定的なのは、英金融政策の不透明感だ。
製造業が落ちこむ一方、稼ぎ頭だった銀行業も危機的な状況にある。業界全体が今後3~4年の間に7920億ドルの不良債権を処理しなければならないという研究報告があるほどだ。
■政局は混迷、金融政策は不透明な英国
次に、英政局の混迷だ。
現在与党の労働党と野党の保守党は5月の選挙でいずれも多数派にならないといった見通しがあり、政局の混迷が続けば、今後英国は財政赤字削減に取り組むどころか、財政赤字を逆に拡大させる恐れさえある。
このような不信感が広まるなか、英ポンドが買われる展開は想定しにくい。
最後に、もっとも決定的なのは、英金融政策の不透明感だ。
英中銀(イングランド銀行、BOE)の声明文を読めば読むほど、英国は利上げばかりか、再度量的緩和に踏み切る可能性もあるといったニュアンスが読み取れる。
米国も利上げは不透明、ユーロもしばらく利上げできない、といった見方はあるものの、量的緩和に逆戻りするリスクのある英ポンドに比べれば、まだ随分マシだと思わざるを得ない。
以上のように、ギリシャ問題が鏡だとすれば、そこに映るのが英国であることは現状のマーケットが物語っている。
■今年の流行語は「ポンドキャリートレード」!?
2009年に「ドルキャリートレード」という言葉が流行ったように、今年は英ポンド安が一段と進行すれば、「ポンドキャリートレード」という言葉も出てくるだろう。
「円キャリートレード」ならぬ「英キャリートレード」ということだ。
もっとも、「キャリートレード」という言い方に筆者はかなり違和感を覚えるのも事実。以前の本コラムでも指摘しているように、ドルキャリートレードは幻想であったはずだ(「原油決済通貨の変更などバカバカしい話。ドル安はこのあたりでクライマックスか?」参照)。
通貨の下げはトレンドに沿ったモメンタムによって進行し、必ずしもその通貨を借り入れて、それを高金利通貨に「投資」した結果ではないのだ。このあたりの説明はまた改めて行いたい。
ところで、米ドル全体の上昇はすでに最終段階であり、そろそろ頭打ちしてもおかしくないという見方は前回も記したが、来るべき米ドル全体の下落があれば、米ドルに対する英ポンドの下落も一服することが考えられる。
今年、英ポンドの「キャリートレード」があるとすれば、対米ドルよりも対豪ドル、対カナダドルなど資源国通貨のほうがより鮮明であろう。
米国も利上げは不透明、ユーロもしばらく利上げできない、といった見方はあるものの、量的緩和に逆戻りするリスクのある英ポンドに比べれば、まだ随分マシだと思わざるを得ない。
以上のように、ギリシャ問題が鏡だとすれば、そこに映るのが英国であることは現状のマーケットが物語っている。
■今年の流行語は「ポンドキャリートレード」!?
2009年に「ドルキャリートレード」という言葉が流行ったように、今年は英ポンド安が一段と進行すれば、「ポンドキャリートレード」という言葉も出てくるだろう。
「円キャリートレード」ならぬ「英キャリートレード」ということだ。
もっとも、「キャリートレード」という言い方に筆者はかなり違和感を覚えるのも事実。以前の本コラムでも指摘しているように、ドルキャリートレードは幻想であったはずだ(「原油決済通貨の変更などバカバカしい話。ドル安はこのあたりでクライマックスか?」参照)。
通貨の下げはトレンドに沿ったモメンタムによって進行し、必ずしもその通貨を借り入れて、それを高金利通貨に「投資」した結果ではないのだ。このあたりの説明はまた改めて行いたい。
ところで、米ドル全体の上昇はすでに最終段階であり、そろそろ頭打ちしてもおかしくないという見方は前回も記したが、来るべき米ドル全体の下落があれば、米ドルに対する英ポンドの下落も一服することが考えられる。
今年、英ポンドの「キャリートレード」があるとすれば、対米ドルよりも対豪ドル、対カナダドルなど資源国通貨のほうがより鮮明であろう。
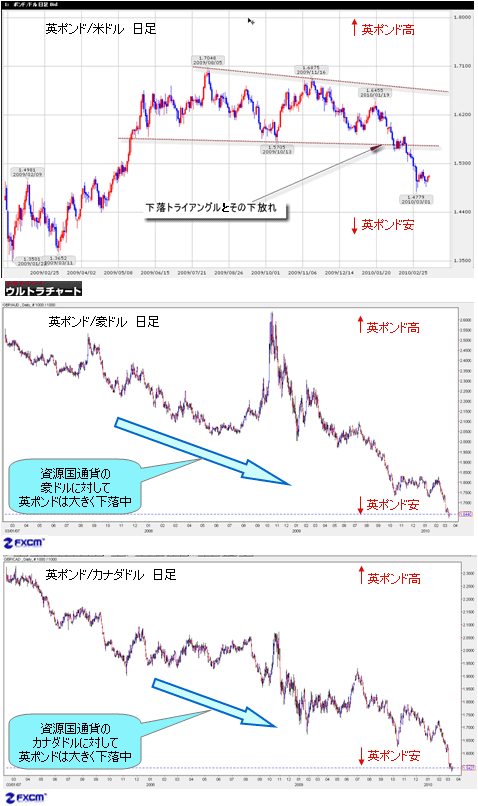
また、キャリートレードのコンセプトを否定した視点からも、英ポンドの対ユーロ、対円での下げはこれからも続く公算が高いとみる。
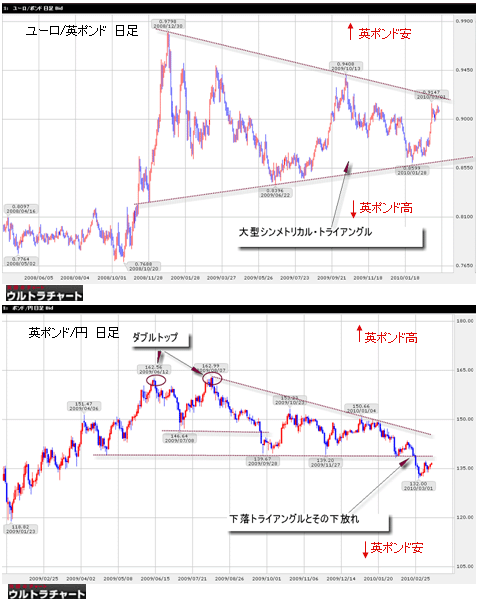
最後に、英ポンド安はテクニカル・アナリシスの視点からも当然の結果と思われ、その進行が続く公算が高いと考えられる。
この点については、上に合計5つ掲載した、英ポンドが絡んだ通貨ペアの各チャートを参考にしていただきたい。

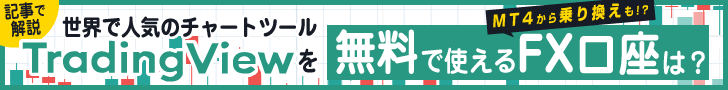












![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)








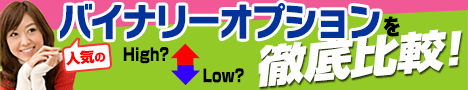
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)