昨日はアメリカが休みだったので、マーケットは小動き。多少の上下動はあったものの、1日の始値と終値が同じになるくらいに相場は戻ってきている。そして今週注目されているのは、日銀の次期総裁が週の後半に国会で意見を述べることだ。金融政策についてあり方が議論されているが、それにともなう長期金利の上昇について考えてみよう。
国債の利回りが上昇するのを嫌って、日銀は異常な金融緩和を続けているという。金利が上がるのだから企業や家計を苦しめることになるのはもちろんだが、国債の大部分を保有している日銀と政府の場合ではどうだろうか。
大量保有している日銀は国際価格が値下がりするのだから、膨大なキャピタル・ロスを抱えることになる。一方で政府は抱えている1000兆円以上の借金の利息が上がるのだから破綻に向かうかもしれず、これまた苦しいときている。これでは誰でも得をする人がないではないかという構図になる。果たしてそうだろうか。
日銀は国債を買って持っているのだから、立場としてはロングである。一方で政府の方はお金があったら国債を買い戻す宿命にある立場なので国債ショートである。立脚すべきポジションがまったくの反対なのだ。どちらかが得をすれば、もう一方は苦しくなるはず。発行している側とそれを購入している側の双方が苦しくなるとは、何か論理矛盾を含んでいないだろうか。
国債を買って持っているというのは、長期にわたって利回りを固定するということである。だからその間の他の物件への投資機会を犠牲にしているのである。保有中に利回りが上昇したら、それは無駄な投資に長期観に渡ってお金を使ってしまったと言うことで、やはり損失だ。それは債券価格の下落となって現われる。
仮に債券を満期まで保有すれば満額戻ってくるのでロスはないじゃないかという考えもあるが、それでもその間の金利上昇分を享受できていないことに変わりはない。日銀の減資は公的資金なのだから、きちんと運用できていないということでは税金の無駄遣いということになる。
債券の発行体である政府の場合はどうか。これから発行する国債に対しては、確かに利回りが上がると支払い利息も増えるので、利払い負担は増える。しかし金融マーケットでは市場で決まるレートで取引する分にはロスはないと見なす。すぐに反対売買すれば損は出ないので、評価損はゼロだと言うわけだ。市中金利が10% のときに10%で借りても、それは損も得もないということ。負担が増えるというのは借り手の事情であって、金融リスクはない。
それとは変わって既発債の方はどうだろうか。金利が上がっているのだから負債の評価は目減りするのは明らか。江戸時代に何度も行った貨幣の改鋳と同じで、政府の収入になる。政府としてはこの収入分で、将来の負担増をまかなうことになる。
結果として既発債をたくさん持っている日銀が金利上昇において巨額な損失を被り、政府が債務の目減りというメリットを得るのである。
日本時間 15時00分
| 【2026年2月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年2月2日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!


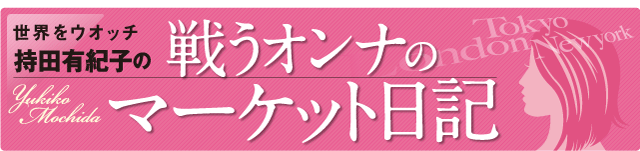
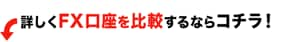
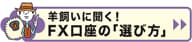


















![ヒロセ通商[LION FX]](https://zaifx.ismcdn.jp/mwimgs/c/f/-/img_cf441770d8ee58a063c99fd812f7fc7a76045.gif)
![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)
![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)







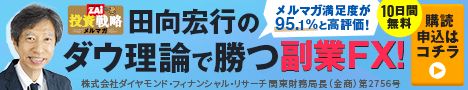
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)