「トランプ・ラリー」が続いている。
トレンドの進行が続くうちは、あとを追う形で次から次へと新しい材料が出てくる傾向があるが、今回も然りである。
■OPECの減産合意で再びリスクオンに
一昨日(2016年11月30日)、合意難航と言われたOPEC(石油輸出国機構)が、珍しく減産に合意した。これを受け、原油の急騰とともにリスクオンのセンチメントが再度刺激され、株高・円安・金安といった典型的な連鎖反応を引き起こし、米ドル/円は114.83円まで続伸した。

(出所:CQG)

(出所:CQG)

(出所:CQG)

(出所:CQG)
米ドル/円のオーバーボートは、前回コラムの指摘どおりだったが、このような材料に、さらに反応せずにはいられなかった。
【参考記事】
●正体はショート筋が踏み上げられたこと! スピード違反のトランプ・ラリーも終焉近し(2016年11月25日、陳満咲杜)
■「トランプ・ラリー」は一種のブラックスワンか
2008年のリーマンショックのあと、ブラックスワン理論が流行った。同理論とは、「『ありえないし、起こりえない』と思われていたことが、いったん急に起こってしまうと、予測できない、非常に強い衝撃を与える」というものだが、同定義に沿った形で今回の「トランプ・ラリー」を見てみると、これも一種の「ブラックスワン」ではないかと思う。
なにしろ、トランプ氏の当選は予想されておらず、また、当選した場合はいわゆる「トランプショック」が想定されていたから、当選が確定した日(11月9日)から大逆転して、その後、一本調子の株高・円安・金安という進行は、どれも「ありえないし、起こりえない」とされる市況だった。
が、「ブラックスワン」と呼ばれていないのは、株が急落ではなく、急伸したからだ。
いわゆる金融危機は、株の暴落を伴っている。そして、当然のように、株安は「悪」である。
しかし、為替の世界はそもそも通貨の交換関係の上に成り立つもので、米ドル高か円高かという違いはあっても、米ドル高は良い、円高は良くないといった区別はできない。したがって、今回の「トランプ・ラリー」は、少なくとも円の立場からみると、「ブラックスワン」と呼んでも間違いがなかろう。
■白いスワンでも黒いスワンでも、株が上がれば歓迎
実は「ブラックスワン」という表現は、やや過激ではあるが、今回の「トランプ・ラリー」の本質をよく説明できるかと思う。
つまるところ、今だからこそ猫も杓子も「トランプ・ラリー」をあおっているが、実は彼らは今まで「ホワイトスワン」しか想定していなかった。また、「ブラックスワン」が出現しても、「たまたま」彼らが事前に予想していた株高・円安が大きく進行しているから、都合がよいというわけだ。
ウォール街の面々は、直近までクリントン氏の勝利に賭け、精一杯、氏を応援してきた。なにしろ、ウォール街はトランプ氏の勝利となった場合は、株暴落を想定し、また、それにおびえていたのだ。
ところがふたを開けてみると、予想はまったく外れたものの、相場の反応は事前の「クリントン氏当選の株高」と同じであるばかりか、想定をはるかに超えた株高の進行が確認された。
よって、鄧小平氏の「白いネコでも黒いネコでも、ネズミを捕るネコはいいネコだ」と言わんばかりに、「白いスワンでも黒いスワンでも、株を上げるスワンは歓迎されるスワンだ」というのである。ウォール街のロジックは実に単純明快だ。
予想外、また、事前に「ありえない」と思われる市況だからこそ、「ありえない」オーバーをしがちで、足元の米ドル/円はその好例であろう。
実際、米ドル/円11月の上昇幅は、1995年以来の記録を更新、「トランプ・ラリー」自体がいかに「ブラックスワン」で、いかに強い衝撃をもたらしたかを物語る。

(出所:CQG)
■トランプ氏の政策方針が抱える3つの矛盾
しかし、トランプ氏の施政方針や理念は、最初から多くの矛盾を抱えていた。氏自身のキャラクターと相まって、インテリ層にバカにされてきた理由もそこにあった。
言ってみれば、トランプ氏は当選したものの、彼が白人をメインとした中産階級の危機感をあおったところは成功だったとしても、根本的には、彼の施政方針が理解され、また、支持されたものでは決してなかった。なぜなら、氏の主張は、少し常識があれば、あまりにも大きな矛盾があることがすぐわかったはずだからだ。
細かいところ、また、経済領域以外の部分での矛盾を除くと、トランプ氏の施政方針と理念は、主に以下の3つの矛盾点を抱えていると指摘できる。
1.インフラ投資拡大と保護貿易主義は共存できない
2.インフレ期待と強い米ドルは同時達成できない
3.金融自由化と貧富の格差縮小は同時にめざせない
いわゆる「トランプノミクス」ともてはやされる氏の主張は、積極財政と大型投資を標榜しながら、「メード・イン・アメリカ」にこだわる保護貿易、製造業保護主義の姿勢をとる。この両者は矛盾する。
アメリカの鉄道運送量の増減が、一貫して諸外国貿易量の増減と高い相関性を示しているように、トランプ氏が本当に大型国内投資を推進していくなら、彼が主張しているように外国からの移民を追い出すのではなく、もっと多く受け入れていかないといけないし、米企業の本土回帰を強要するのではなく、もっと積極的に諸外国と自由な貿易関係を作らなければならないはずだ。

トランプ氏の政策には大きな矛盾あり!? 大統領就任後にその矛盾の辻褄をどう合わせるのか注目かも… (C)Scott Olson/Getty Images
このあたりの知識を、ウォール街の面々は十分持っているはずが、株高をもたらした「ブラックスワン」に、誰も「あいつはブラックだ」と言わなくなっている。
ましてや、トランプ氏はウォール街出身者を重要ポストに起用することを考えているため、ウォール街は今はトランプ政権との「蜜月」を演じなければならない。今はあえて目をつぶっているはずなのだ。
■次のターゲットは120円より110円の方が現実的!
もちろん、ウォール街とはいえ、すべてがそうとは言えない。
債券王ビル・グロス氏はトランプ氏が4年の大統領任期を全うできないと予想しているし、新債券王のジェフリー・ガンドラック氏は「トランプ・ラリー」が、トランプ氏が正式に米大統領に就任するまでで終わるだろうと警告している。
そして、筆者としては、「トランプ・ラリー」はそこまで待たず、今月(12月)の米利上げ前後までしか続かないのではないかと思う。
このあたりの考え方や、トランプ氏施政方針の矛盾に関する詳説は、また次回に譲るが、米ドル/円に関しては、「トランプ・ラリー」のさらなる行きすぎがあってもせいぜい116円台で終わり、また、次のターゲットは120円よりも110円の方が現実的、という結論を記しておく。市況はいかに。














![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)







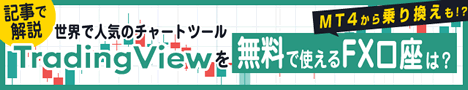
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)