先週は人民元の弾力化について述べたが、もう一つの焦点である米FRB(連邦準備制度理事会)のハト派スタンスの表明については、今週になってからその意義がより鮮明になっている(「5年サイクルで見て今は円安トレンド。人民元弾力化による円高進行は続かない」参照)。
■格付け会社は事後的に格付けするしか能がない!
格付け会社は相変わらずPIIGS関連金融商品を格下げの方向に動いてるものの、ユーロは対米ドルで上昇し、ユーロ/米ドルは1.2500ドルに乗せてきた(※)。事後的な格付けしか能のない格付け会社は本領をこれから発揮してくると予想されるが、マーケットは食傷気味で、もはや反応しなくなってきている。
その大きな背景には、筆者がずっと指摘している米ドル全体のトップアウトという可能性がある。
(※編集部注:「PIIGS」とは欧州で財政面に不安があると言われるポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペインを指す言葉)
(出所:米国FXCM)
それとリンクすることだが、米ドルの全面安を引き起こす直接の材料として、マーケットの焦点が明らかにEUのソブリンリスク(国の債務に関するリスク)一辺倒から、米国サイドのリスクに移っていることが挙げられる。
最近は米経済データの弱さが目立っており、米FRBのハト派スタンスを追認する形となっているのだ。
■米国株と米国経済はこれから「失われる10年」を迎える
実際、最近中国株の下落が世界株安をもたらしたと解釈され、米国経済の二番底懸念が高まったことから、米ドルが売られてきたと言われているが、筆者としては、以下の2点を指摘しておきたいと思う。
まず、中国株の下げや中国経済のハードランディングの可能性が、そのまま欧米株(日本株を含む)の下げの要因として解釈されるのは間違いである。
簡単に言えば、欧米株の下落はそれらの市場の内部構造に沿った値動きと言える。
そして、現在の下げは序の口で、米国株と米国経済はこれから「失われる10年」を迎えるだろう(このあたりの話について、筆者はCFD関連講演でよく論議してきたし、自らが米国株のショートポジション(売りポジション)を持っている根拠でもある)。
■上海万博開催なのになぜ中国株は冴えないのか?
中国経済と世界経済の動向はかなり乖離しているため、中国株のパフォーマンスは基本的には物差しとして使えないから、前述した論議は根本的に間違っている。
もっとも、上海A株のパフォーマンスはギリシャと並び、年初来世界のワースト1、2に並べられるほどだ。ギリシャなら納得できるが、証券会社の宣伝に煽られて、上海万博云々の理由で中国株を買った方々はさぞかし落胆していることだろう。
しかし、これにはワケがある。
それとリンクすることだが、米ドルの全面安を引き起こす直接の材料として、マーケットの焦点が明らかにEUのソブリンリスク(国の債務に関するリスク)一辺倒から、米国サイドのリスクに移っていることが挙げられる。
最近は米経済データの弱さが目立っており、米FRBのハト派スタンスを追認する形となっているのだ。
■米国株と米国経済はこれから「失われる10年」を迎える
実際、最近中国株の下落が世界株安をもたらしたと解釈され、米国経済の二番底懸念が高まったことから、米ドルが売られてきたと言われているが、筆者としては、以下の2点を指摘しておきたいと思う。
まず、中国株の下げや中国経済のハードランディングの可能性が、そのまま欧米株(日本株を含む)の下げの要因として解釈されるのは間違いである。
簡単に言えば、欧米株の下落はそれらの市場の内部構造に沿った値動きと言える。
そして、現在の下げは序の口で、米国株と米国経済はこれから「失われる10年」を迎えるだろう(このあたりの話について、筆者はCFD関連講演でよく論議してきたし、自らが米国株のショートポジション(売りポジション)を持っている根拠でもある)。
■上海万博開催なのになぜ中国株は冴えないのか?
中国経済と世界経済の動向はかなり乖離しているため、中国株のパフォーマンスは基本的には物差しとして使えないから、前述した論議は根本的に間違っている。
もっとも、上海A株のパフォーマンスはギリシャと並び、年初来世界のワースト1、2に並べられるほどだ。ギリシャなら納得できるが、証券会社の宣伝に煽られて、上海万博云々の理由で中国株を買った方々はさぞかし落胆していることだろう。
しかし、これにはワケがある。
■上海A株は「カジノ」マーケットだ!
なぜなら、上海A株は基本的には中央政府の政策動向と流動性に左右されるマーケットで、企業業績とはあまり関係ない「カジノ」マーケットであるからだ。
もちろん、上海A株の動向に強く影響される香港H株も基本的には一緒で、これを理解せずには中国株に投資すべきではない。
なぜなら、上海A株は基本的には中央政府の政策動向と流動性に左右されるマーケットで、企業業績とはあまり関係ない「カジノ」マーケットであるからだ。
もちろん、上海A株の動向に強く影響される香港H株も基本的には一緒で、これを理解せずには中国株に投資すべきではない。
上海総合指数 日足

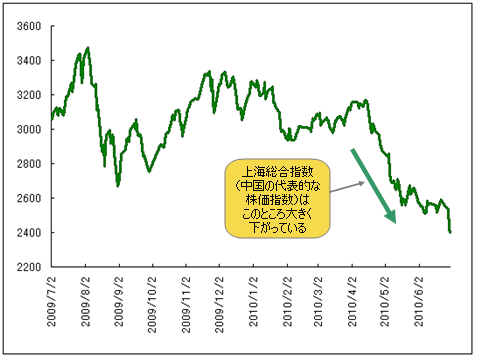
余談であるが、昨日テレビで某有名中国株の専門家が「業績見通しがいいのに、なぜ中国株が下がるかわからない」と発言していた場面を見た際、筆者は逆に少しショックを受けたほどだ。
ちなみに、筆者は今年中国株をまったく買っていない。ややおかしな根拠に思われるかもしれないが、北京オリンピック前後の中国株の暴落と同じく、上海万博は買い材料ではなく売り材料とみていたからだ。
このようなジンクスが正しければ、ワールドカップ云々、ブラジルオリンピック云々の宣伝には十分用心すべきだろう。
■米国株と米ドルの関係は?
次に、米国株と米ドルのパフォーマンスについてだが、両者の関係が常に一定と考えるのは間違いだ。
米国株の下落がリスク回避の動きを喚起し、米ドルが買われるといった発想が常に正しいとは限らない。これからは恐らく逆のパターンに動くのではないかと思う。
ユーロ/米ドルとNYダウ 日足

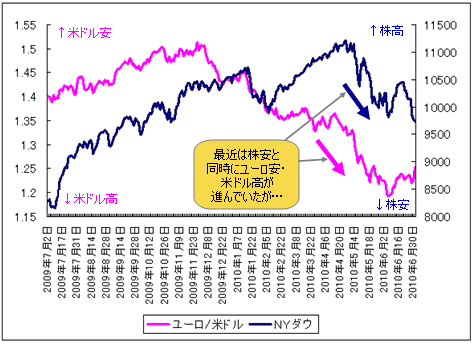
すなわち、米国株の下落はそのまま米国ファンダメンタルズの弱さとして解釈され、米ドルもそのまま売られる羽目になるだろう。要するに、米ドルはリスク回避先と見なされない可能性が大きいということだ。
短期的なスパンはともかく、歴史的なデータを検証すると、米国株と米ドルのパフォーマンスは大した相関性を持っていないことがわかる。従って、これからは米国株と米ドルのパフォーマンスを基本的にわけて考える必要が出てこよう。
■世界景気後退の可能性は高い。その時、米ドルは?
まとめると、筆者は世界景気後退の可能性が高いという論には同調できるが、それをもって米ドル高(対円を除く)、円高の根拠とする論議には同意できない。
いずれ、米国を中心とした景気後退がそのまま米ドルの売り圧力として解釈される日が遠からず来ると見ている。ただし、その進み方は緩やかだろう。
また、米ドル安の進行につれて、他の主要通貨のファンダメンタルズに不思議なくらいプラスの材料が出てこよう。
最近では、英ポンド高につれ、英緊縮財政案に対する評価が高まり、英早期利上げの可能性が囁かれ始めたことが挙げられる。また、ユーロについては、ギリシャ政府が赤字削減計画の早期達成可能性について表明したことなどがその好例と言えるだろう。
■今後10年で人民元は米ドルに対し、倍以上に上昇!
一方、中国株や中国経済のハードランディングの有無について筆者は確信できずにいる。
筆者が知る限り、西側を中心に、中国の激変に関する予想は一貫して裏切られてきた。恐らくハードランディングがあったとしても、人々の想定より早く立ち上がることだろう。
大国の底力は危機を克服する時に発揮される。中国の勃興サイクルは少なくとも今世紀半ばまで続くという見方が支配的だ。
その意味では今後10年間、人民元は対米ドルで倍以上の上昇幅があるとみている。ただし、中国に対する過大な期待を振り払うために、1回大きなクラッシュがあってもおかしくないだろう。
ところで、先週、筆者は人民元の弾力化が円高の根拠にならないと論じたが、足元では円高の進行が一段と進んできた。それでも筆者は目下の円高には限界があるとみている(「5年サイクルで見て今は円安トレンド。人民元弾力化による円高進行は続かない」参照)。
その根拠は次回分析したいと思う。
最後にご報告を。筆者は近々通貨ペアの値動きを天気予報にたとえた「為替天気予報」というメールマガジンを立ち上げる予定だ。無料なので、ザイFX!読者の皆様にもぜひご覧いただければ幸いである(メールマガジンの詳細は、私のブログ「為替の真実」をご参照ください)。

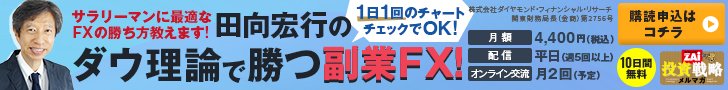

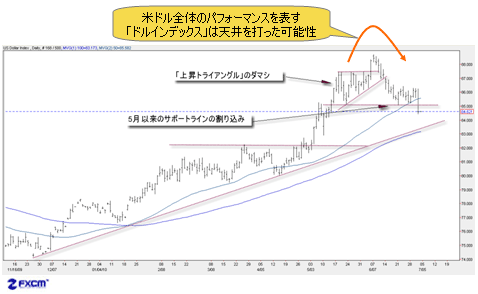











![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)









株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)