■米ドル/円は予想より早く100円を突破!
米ドル/円は100円の心理的な大台に乗せてきた。先週(11月4日~)の波乱を経て、米ドル/円の保ち合い状況を打破するには、もう少し時間がかかると思っていたが、リスクオンムードの再開で早期転換を果たした模様。
検証サインとして、前回のコラムで指摘しておいた11月7日(木)の大陰線の高値・安値、どちらかを先にブレイクするかは重要であった。
【参考記事】
●「ドラギ・ショック」と「米GDPショック」で波乱の相場!ドル/円の上放れは先送り?(2013年11月8日、陳満咲杜)
今週火曜日(11月12日)には、11月7日(木)高値の99.41円を更新していたから、これが現在までの上昇をもたらしたわけだ。
(出所:米国FXCM)
もっとも、米ドル/円の上放れが下放れより確率が高いことを予測するのは、難しい理論とテクニックなどなくても十分可能であった。
上のチャートが示しているように、上昇傾向を続ける200日移動平均線(200日線)のサポートが、10月以来3回も確認されている。先週木曜日(11月7日)の大陰線もしかりであった。
ザラ場にて200日線を下回ったことはあったものの、引け値がすべて同線の上にあったことは、米ドル/円地合いの堅調を示唆するサインである。同サインを重視すれば、上放れを当然の成り行きとみなし、高値更新後の追随買いも極めて自然な判断と行動である。
■英ポンド/円はいち早く「アベノミクス相場」以来の高値更新
円安トレンドの進行で、より目立つパフォーマンスを達成しているのは、英ポンド/円である。「アベノミクス相場」以来の高値を更新し、2009年8月高値に迫る英ポンドの上昇はクロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)をリードする役割を果たしている。
すでに161円の節目を打診しているので、10月25日(金)の本コラムにて指摘していた162.29円という中期ターゲットは、もはや短期目標としてもあり得る状況だ。
【参考記事】
●ドル安は陰の極まり。ドル/円は96.56円を下回らない限り、三角保ち合い上放れか(2013年10月25日、陳満咲杜)
(出所:米国FXCM)
英ポンド/円の上放れポイントは、上のチャートに記しているトライアングルの上放れにあった。一昨日(13日)に上放れを果たしていたから、米ドル/円の上放れと相俟って、円安トレンドを推進するサインとして読み取れたわけだ。
また、英ポンド/円の高値更新が米ドル/円より早く達成されたのは、200日線1本の観察でも納得できる。
米ドル/円は200日線の再三の打診をもってサポートを確認したのに対し、英ポンド/円はレンジの上乗せによって上昇モメンタムを維持してきたし、2012年9月以来、1回も200日線を打診していない。
つまり、英ポンド/円のほうが米ドル/円よりずっと堅調な地合いを維持してきたから、英ポンド/円が米ドル/円より先に高値を取っていくのも当然の成り行きなのである。
■ユーロ/円は100日線を割らない限りブルトレンド継続か
英ポンドに比べ、遅れを取っているユーロ/円だが、これから高値を更新し、同じく10月25日(金)の本コラムにて指摘した上値ターゲットに照準を合わせる公算が大きいとみる。
【参考記事】
●ドル安は陰の極まり。ドル/円は96.56円を下回らない限り、三角保ち合い上放れか(2013年10月25日、陳満咲杜)
注目していただきたいのは、ユーロ/円は2013年6月以来、再三にわたって100日線のサポートを確認し、先週、11月7日(木)のECB(欧州中央銀行)利下げ後も同線のサポートを確認してから切り返してきたということだ。
だから、100日線を本格的に割らない限り、ユーロ/円のブル(上昇)トレンドは続くといった見方は妥当であろう。
(出所:米国FXCM)
■米ドル/円は「押し目待ちに押し目なし」の可能性も
話を米ドル/円に戻すが、次のチャートに記しているように、5月高値から、約5カ月半にわたって形成された大型トライングル型の保ち合いは、調整波に当たる。そして、同トライアングルの上放れをもって、推進波の始動が示唆された。
(出所:米国FXCM)
前述の調整波は、期間が長かっただけに、いったん推進波を始動した場合、比較的上昇モメンタムが強くなる傾向にあるから、これがこれからの市況を検証するひとつのヒントになる。
言い換えれば、米ドル/円の上放れがホンモノであればあるほど、上昇モメンタムとスピードは速いはずである。逆にここからの値幅が限定的で、なおかつスピード感のない相場が続くなら、何らかの理由により、ブルトレンドが再度挫折する可能性がある。
ゆえに、これから米ドルの上昇がホンモノであれば、「押し目待ちに押し目なし」といったリスクも想定しておきたい。
■最大のリスクは「楽観的すぎる市場センチメント」
ところで、相場というものは、一点の曇りもないという状況はあり得ない。一部市場関係者から米ドル高の継続を疑問視する声も大きい。もっとも指摘されているリスク要因は、市場センチメントの「楽観すぎ」である。
今回の米ドル/円の上放れは、タイミング的にはイエレンFRB(米連邦準備制度理事会)副議長の議長昇格を審査する時期に重なる。
FRB記者会見や米公聴会などにおいてイエレン氏の発言を聞く限り、イエレン氏はバーナンキ氏の緩和路線を踏襲し、はっきりした景気回復の兆しがつかめないうちは安易な出口戦略を講じない意向が鮮明である。
その上、仮にQE(量的緩和策)縮小策に踏み込んだとしても、それは段階的な措置に留まり、マーケットにインパクトを与えないように慎重策を取るだろうことが読み取れる。
マーケットは氏のスタンスを好感し、NYダウやS&P500といった米国の株価指数は、昨日(11月14日)も高値を更新している。もちろん、史上最高値である。
(出所:米国FXCM)
こういった雰囲気の中、米国株を始め、マーケットの楽観ムードは行きすぎではないかと危惧する声も多い。
■低すぎるVIX指数(恐怖指数)が逆にリスクを示唆している
それを証左するように、VIX指数、つまり恐怖指数の低下を警戒のサインとして挙げる向きも多い。
VIX指数は相場の変動率に基づき計算されたものだが、同指数の急上昇は往々にしてマーケットの急落を伴うから、恐怖指数と呼ばれるわけだ。
一方、同指数が、低下し続けて極端に低い値を示しているのも、同じく恐怖を市場参加者に与える。最近のVIX指数の動向は、それに当たるのだ。
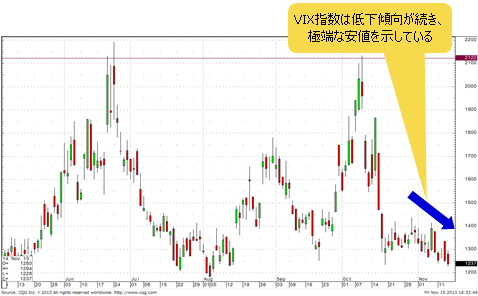
(出所:CQG)
要するに、低すぎて安値圏にある同指数は往々にしてマーケットの「楽観すぎ」に起因しているから、偏った市場センチメントの逆転でその後マーケットの急落につながるケースが多いのだ。
FRBの政策継続を好感するマーケットは、株価指数の史上最高値更新をもってVIX指数を押し下げているが、それはいつかどこかで反転するリスクを抱え込んでいるのである。マグマは溜まっているというわけだ。
■進行中の円安相場に乗らないのはもったいない
では、トレーダーとしては、この相場にどう対応すべきだろうか。筆者の答えはシンプルだ。100年に一度の地震がもうじき来ると聞いて、みなさんは日本を離れて外国に逃げただろうか。逃げていないなら、今の生活と仕事の方が大事だということになる。
同じことが相場にも言える。リスクオンの行きすぎで、いつか相場が反転するとはいえ、それがいつ来るかがわからない以上、我々は今のポジションを堅持するほか選択肢はない。
もちろん、防震グッズを家に常備するように、しっかりリスクコントロールをすれば、目下進行中の円安相場に十分乗れるし、乗らないともったいないと思う。このあたりの話は、また次回に。



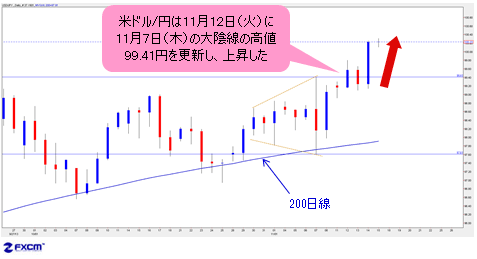
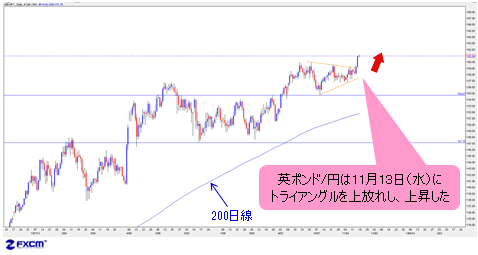
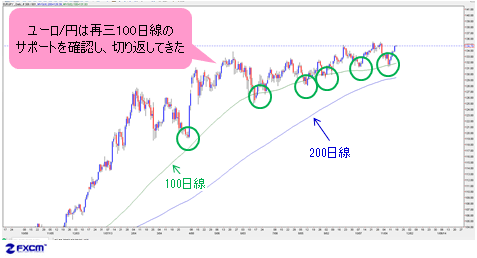
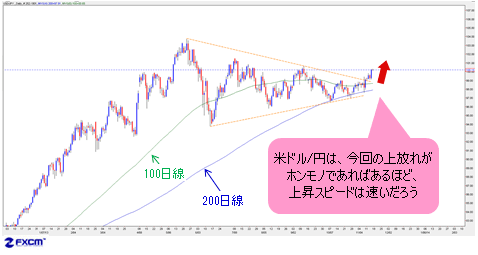
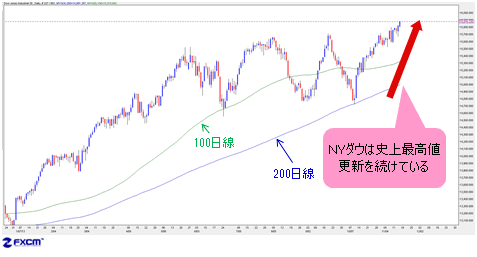











![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)








株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)