■黒田日銀総裁のジレンマとは?
10月末の日銀の追加緩和は一番大きなサプライズだったと言えるが、最近もサプライズと言える材料が続出している。中国利下げにOPEC(石油輸出国機構)減産見送り、そして今朝(11月28日)発表された10月CPI(消費者物価指数)の1%割れ(実質)が、それに当たる(※)。
何しろ、かつて黒田日銀総裁が「割れることはない」と公言した1%の基準を下回ったのだから、黒田さんの誤算が続くという格好に。もちろん、安倍さんの増税見送りが黒田さんにとって最大の誤算であったに違いない。
(※編集部注:10月のCPI(消費者物価指数)は、生鮮食品を除いたコアCPIが前年同月比2.9%上昇。4月の消費増税分を除いた上昇率は0.9%程度とみられている)
ここで、シェイクスピアの「to be or not to be(※)」の名台詞が、黒田さんの頭に繰り返し響いているのではないだろうか。
未踏の領域に入った日銀の異次元緩和は、実質「本家」のアメリカを超える規模になったにもかかわらず、想定期間(2年)内にインフレターゲット(2%)を達成できないのなら、責任を問われるのも当然だ。
そこでジレンマが生じてくる。黒田さんが言うように、目標達成するまで「躊躇なく政策推進」なら、さらなる追加緩和が必要になってくる。また、中途半端になれば、前の緩和が台無しとなり、かえって悪影響が大きい。
しかし、さらに追加緩和を決定しても、インフレターゲットを必ず達成できるという保証はなく、すでに出口政策の難しさが指摘された日銀にとって、さらなる追加緩和の実施は自ら出口をふさぐような行為に等しい。
(※編集部注:“To be,or not to be : that is the question”はウィリアム・シェイクスピア作の悲劇『ハムレット』の台詞。「生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ」といったようによく日本語訳されるが、この場合は「すべきか、すべきでないか」という意味。「量的緩和をさらに推進すべきか、すべきでないか、それが問題だ」)
■日銀内部にも軋轢? 黒田氏の思いどおりになるかは微妙
このような懸念は、日銀内部でもわき上がっているので、黒田さんの内心は、少なくとも表向きのように穏やかではなかろう。
先日(11月26日)、白井日銀審議委員はインタビューで「追加緩和は、現在とり得る最大限のもの」、「見通しが下振れても、機械的な追加緩和はない」と言い切った。日銀内部の亀裂を暗示しているかのような発言内容は興味深いところだ。
10月末の追加緩和がそもそも「5対4」の僅差で可決されたことから考えてみても、次回も黒田さんの思うままに進むかどうかは、微妙になってくるだろう。
もっとも、消費税再増税の延期なしが追加緩和の前提条件であることを黒田さん自身が話していたから、安倍さんの見送り判断は、日銀や財務省から見れば、「裏切り」というほかあるまい。
その上、2017年に「決定」した再増税が、何らかの理由でまた先送りされる可能性は決して小さくはないから、日銀は「疑心暗鬼」で、すでに史上初の異次元緩和をさらなる異次元に推し進めていく「モチベーション」が低下しているに違いない。
中国の民間のことわざを借りると、「官」は口が2つもあるというから、いつ、どのような発言が出てきても驚くことなかれ。2017年の消費税アップは、いわゆる「景気条項」が撤廃されたから、間違いなく実行されると思う方は、自民、民主を問わず、かつての政治家の公約違反事例を点検してみれば、自信をなくすかもしれない。
■原油相場の暴落が結局は株高・円安トレンドに寄与
閑話休題。要するに、第3回量的緩和は本当のところ確実ではないにもかかわらず、マーケットは今のところ、確信をもっているだろう。こういった市場センチメントが維持される限り、目先、株高・円安のトレンドも維持される公算が大きい。
冒頭で記したように、原油の暴落があったにもかかわらず、OPECは減産を見送り、昨日(11月27日)、これが原油相場の崩れをもたらした。
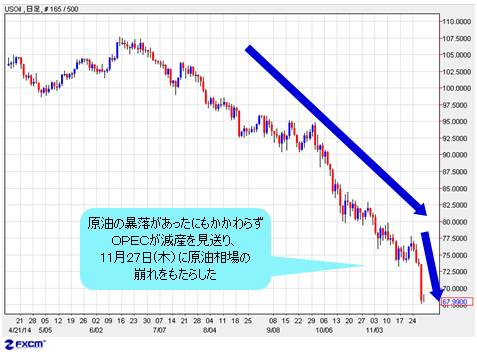
(出所:米国FXCM)
原油価格の低下はCPIを押し下げる原因の1つとして認識されるから、原油相場の「底なし」が日銀の第3回量的緩和の期待を高め、株高・円安トレンドに寄与していることは確かだ。
もっとも、日銀緩和策の中には、ETF(上場投資信託)の直接購入が含まれているから、マーケットは「緩和中毒」気味だ。緩和政策で買われた株が高くなるにつれ、一段と緩和策を期待するようになるといった具合だ。
ゆえに、マイナス材料はかえって株高期待を高める効果がある。インフレに関する指標なら、なおさら都合がよい。それと連動した円安も当面維持されるだろう。
よって、米ドル/円もユーロ/円も、かなりオーバーボートの状況にあるが、前記市場センチメントが支配的になっている以上、米ドル/円の高値更新が予想される。
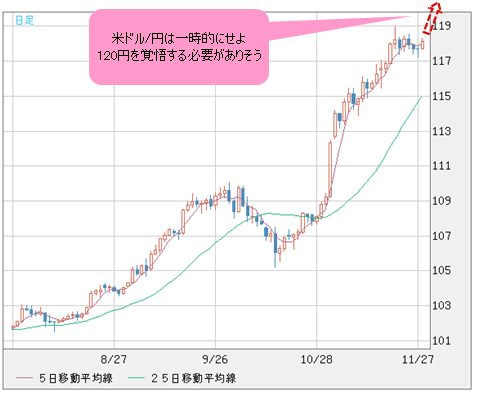
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足)
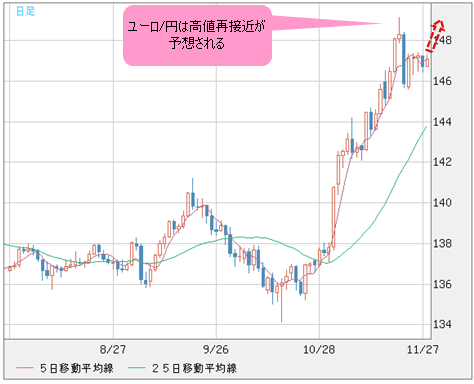
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/円 日足)
米ドル/円に関しては、119.40円前後といった従来の上値計算値のほか、一時的にせよ、120円の節目も覚悟すべきではないだろうか。
【参考記事】
●ドル/円の上値メドは119.4円だが、円安が「解散クライマックス」となる可能性も…(2014年11月14、陳満咲杜)
■相場の転換には次のサプライズを待つ必要がある
目下の相場、円売り自体が円売りを呼ぶ段階にあるから、「臨界点」の達成は、次のサプライズを待たなければならないと思う。
そのサプライズとは他ならぬ、マーケットが確信を増している日銀の第3回緩和予測にある。もちろん、サプライズだから、こういった予測がはずれることや期待の後退リスクが増大してくることはあるだろう。
また、引き続き米国株の動向を中心に、外部要素の異変がサプライズを引き起こす可能性を警戒しておきたい。
米ドル全体については、ECB(欧州中央銀行)のQE(量的緩和)政策が予想されるなか、ユーロの下値余地拡大が市場コンセンサスになっている。
原油の急落がEU(欧州連合)のCPIを押し下げるのは日本と同様なので、ECBの早期行動の有無が材料視されるだろう。予想より遅れた場合、やはり一時のサプライズを引き起こす可能性があるので、注意が必要だ。
■原油相場総崩れはロシア経済に対する米国の陰謀?
最後に、原油相場の総崩れについて、いろいろな説があるなか、ロシアに打撃を与えるための、米国主導の政治陰謀説が目立ってきた。
真相はともかく、仮にこれが事実であれば、1つ言えるのはこの戦略は米国にとって実に一石二鳥の妙案である。
原油に依存するロシア経済に打撃を与える上、EUと日本にデフレ圧力もかけ、米国の代わりに量的緩和をやってもらうということだ。果たして米国の思惑どおりにいくかどうか、そして、市況はいかに。














![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](/mwimgs/c/d/-/img_cd98e6e3c5536d82df488524d85d929d47416.gif)







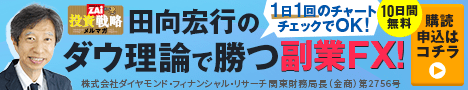
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)