2016年1月29日(金)、日銀はマイナス金利導入を発表。銀行が日銀に預ける当座預金の一部に、マイナス0.1%の金利を適用すると発表したのだ(一般市民が銀行に開設している普通預金口座の金利がマイナスになるわけではない)。
【参考記事】
●日銀のマイナス金利導入で相場大荒れ! 米ドル/円は急上昇→急反落→ジリ上げ
黒田日銀総裁が国会などで、これまで繰り返し、「マイナス金利は具体的に考えていない」と発言していたことなどもあり、今回のマイナス金利導入は市場関係者の間で“基本的には”予想されていなかった(と思われる)。
そのため、この発表は大きなサプライズとなり、為替・株・債券など金融市場は大きく動揺した。
■日銀マイナス金利導入を議論といち早く報道した日経新聞
しかし、日銀がマイナス金利導入を正式発表する前に、それが日銀金融政策決定会合で議論されていることをいち早く報道したメディアがあった。日本経済新聞(日経新聞)である。
日銀が正式発表したのは1月29日(金)の12時38分。その15分前の12時23分ごろに日本経済新聞がウェブサイト上で「日銀、マイナス金利導入を議論」と報じたのだ。
これにより、米ドル/円は118.5円台付近から119.3円台付近まで80銭ほども一気に上昇したが、すぐに反落した。

(出所:ヒロセ通商)
「市況かぶ全力2階建」という金融関連の人気まとめサイトがある。金融市場で起こったおもしろネタについて、さまざまな人のツイートなどを集めて紹介しているサイトだ。
この「市況かぶ全力2階建」のまとめ記事(※)では、日本経済新聞の編集委員氏が「日経新聞発表後、日銀正式発表前」という時間帯に「マイナス金利ですか?」とツイートしているのに対して、個人トレーダーが「こっちが聞きたいです」と返しているという、心温まるやりとりが記録されている。
※記事タイトルは「なぜ日銀の『マイナス金利』は漏洩したのか?金融政策発表直前に出た日本経済新聞の飛ばし記事が市場関係者の間で波紋」
■初心者注意! 日経新聞の事前報道が正しいとは限らない
今回の日銀によるマイナス金利導入には驚かされたが、その直前には上述したようなミニドラマがあり、「日本経済新聞の取材力の高さ」や「日銀会合出席者(?)の情報管理意識の低さ」などにも驚かされたのである。
(※今回の日銀金融政策決定会合には、議決権のある計9名の委員のほか、財務省と内閣府から4名が出席していた)
「そんなことはどうでもいい。我々は相場で儲かれば良いのだ」という向きもいることだろう。また、最近、トレードを始めた人の中には「日経新聞から事前報道があったのなら、日経新聞報道から日銀正式発表の間に、米ドル/円を全力買いしていれば大儲けだったんじゃないの?」と単純に思った人もいるかもしれない。
以下のチャートを見れば、日銀正式発表後の吹き上げ方は、日経新聞報道での吹き上げ方よりかなり大きい。したがって、上述の考え方は結果論的には合っている。

(出所:ヒロセ通商)
しかし、論理的に考えて、日経新聞は「日銀、マイナス金利導入を議論」と報じただけなので、「議論はしたけれど、結果、導入はされなかった」という可能性もある。
また、過去の日経新聞による金融市場を驚かすような報道が、結果的に実現したこともあるが、実現しなかった例もいろいろとある。
日経新聞のサプライズ報道が100%正しいとは限らない。そういう報道にしたがってポジションを取る場合でも、過剰なポジションを取りすぎないなど、リスク管理を考えて、トレードすることをおすすすめしたい。
■今回の追加緩和を予想していたエコノミストは42人中6人
さて、今回の日銀によるマイナス金利導入は市場関係者にとって、完全に予想外の話だったのだろうか? そのあたりについて、今一度振り返ってみたい。
ブルームバーグが2016年1月27日(水)に公開した記事(※)では、エコノミスト42人を対象に日銀金融政策の予想を調査した結果が掲載されている。
(※記事タイトルは「日銀金融政策の市場予想-追加緩和予想時期(表) 」)
この調査によると、日銀が2016年1月に追加緩和に踏み切ると予想していたのは42人中、わずか6人だった。
これはエコノミストではなく、実際に市場に向き合ってトレードしている人たちの見方よりもだいぶ低い数値だと個人的には感じる(数値化できるものではないが…)。
たとえば、ザイFX!で2016年1月26日(火)に公開した西原宏一さん、松崎美子さんの対談記事では、タイトルがいきなり「バズーカ発射へと追い込まれる黒田総裁」となっていたのである。
【参考記事】
●バズーカ発射へと追い込まれる黒田総裁。追加緩和実施ならドル/円はどこまで上昇?(2016年1月26日、た西原宏一&松崎美子)
ただ、追加緩和を予想した場合でも、その手段は長期国債、ETFなどの買い入れを増やすなど、従来の政策の延長線上の追加緩和を予想するケースが多かったと思われる。
その中で、先ほどのブルームバーグの調査に戻ると、「追加緩和の具体的な手段」として、「付利の引き下げ」を挙げていた人が42人中、3人はいた。
「付利の引き下げ」というのは、今まで日銀の当座預金の超過準備に付けられていた0.1%の金利を引き下げるという意味であり、まさに今回行われたこと(さらにそれをマイナスの領域にまですることへ踏み込んだ)。
追加緩和があるとして、そういう手段があることを予想していたエコノミストがわずかではあるが、いたということだ。
ただ、これは調査の回答項目が「付利の引き下げ」としかなっていないので、当該エコノミストが付利を引き下げたとして、マイナス金利への突入までを予想していたか、どうかはわからない。
■「マイナス金利が効果的」と発言していた中島厚志氏
ただ、筆者が調べてみたところ、事前に何かを察知していた人もいたのかもしれないと思うことも多少はあった(「あとから」の話で恐縮だが…)。
1つは2016年1月25日(月)にテレビ東京系の「ニュースモーニングサテライト」(モーサテ)に出演していた経済産業研究所の理事長・中島厚志氏である。
この経済産業研究所というのは経済産業省所管の独立行政法人。そして、言うまでもなく、テレビ東京は日本経済新聞系のテレビ局だ。
中島氏はモーサテの中で、「『逆オイルショック』 不都合な真実」と題して、解説をしていた。1970年代のオイルショック時には強烈なインフレが問題となったわけだが、今は「逆オイルショック」と呼ぶべき状態となっており、世界的なディスインフレなどが起きていることを解説していた。
その最後に、「今回、日銀は追加緩和に踏み切る可能性が強い」と断言しており、手段については「マイナス金利が実はもっとも効果的」とマイナス金利にだけ言及していた。さらに「投機筋の円買いを締め上げる」にはそれが一番いいと話していたのである。
穏やかな紳士にしか見えない中島氏だが、発言内容は結構激しいものだった…かも?
■元日銀副総裁岩田一政氏もマイナス金利が望ましいと発言
また、2016年1月28日(木)に朝日新聞のウェブサイトで公開された、岩田一政氏への取材記事(※)でも、マイナス金利に触れられていた。
(※記事タイトルは「『マイナス金利が望ましい』 元日銀副総裁・岩田一政氏」)
岩田氏は2003年から2008年まで日銀副総裁を務めていた人で、日銀総裁候補と言われていた時期もあった。現在は日本経済研究センターの代表理事・理事長を務めている。日本経済研究センターは民間の研究機関だが、初代理事長は元日本経済新聞社の社長であり、場所は日本経済新聞社の東京本社ビル内にある。
この記事の中で岩田氏は現在の日銀の量的・質的金融緩和政策は限界が近づいており、以下のとおり、ここからやるとしたら、「マイナス金利」が望ましいと述べていた。
「私は『マイナス金利』政策をとることが望ましいと思う。出口における赤字発生を考慮すると、ここまで量的に日銀のバランスシートを拡大してしまったら、金利目標に戻るしかない。伝統的な金融政策の枠内で金利がゼロまで下がってしまい、それ以上下げられなかったから、量的緩和に踏み切った。だが、金利はマイナスにするという手が残っている」
また、マイナス金利の効果としては、「一番明確なのは為替レートへの影響だ。金利をマイナスにまで下げれば、為替レートを円安にすることができる」と話していたのである。
日銀発表前にマイナス金利に言及していた中島厚志氏と岩田一政氏。2人ともその効果として「為替の円安」を挙げていたのが印象的だ。
今回の日銀によるマイナス金利導入は確かにサプライズだったが、政府もしくは日本経済新聞に関係する人たちの中には、もしかしたら、マイナス金利導入を何となくはかぎつけていたのかも…?と思われる人がいたように思われるのだ。
今後のトレードの参考に以上のことをお伝えしたい。
(ザイFX!編集長・井口稔)

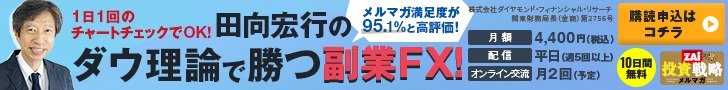












![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)
![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)







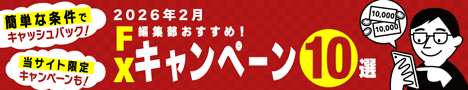
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)