■米長期金利は想定より大きな下落を演じた
8月1日(木)の急反落があって、米ドル/円は8月7日(水)に105.50円の安値にトライした。
前回のコラムでも指摘したように、8月1日(木)の値動きは、本質的には「フォールス・ブレイクアウト」のサインを点灯していたので、安値トライはその結果と受け入れ、また、さらなる下値打診があってもおかしくなかろう。
【参考記事】
●米ドル/円波乱の最大の要因は?トランプ氏の対中ツイートは「きっかけ」にすぎない!(2019年8月2日、陳満咲杜)

(出所:Bloomberg)
もっとも、米ドル/円は米長期金利(米10年物国債利回り)の動向に敏感で、米10年物国債利回りの値動きが最近の米ドル/円を左右している、と見ても間違いではないだろう。
米10年物国債利回りは、8月1日(木)に7月安値1.939%を割り込み、8月7日(水)には一時1.595%の安値を記録、想定よりさらに大きな急落を演じた。

(出所:Bloomberg)
米中対立の激化やFRB(米連邦準備制度理事会)継続利下げの思惑に、米国株の急落もあって、安全資産の米国債への資金流入が一段と激化した結果だと言える。
■米国株はなお、強気基調を保っている
反面、米10年物国債利回りの急速な低下のすべてが、必ずしもリスクオフで説明できるわけではないと思う。
なにしろ、中国人民元切り下げを機に、米国株の急落が再び見られたが、史上最高値からの調整であり、また昨日(8月8日)再度大幅に切り返し、ナスダックに至っては先週末(8月2日)からの下落幅をすべて取り戻したほどの修復ぶりだったので、米国株はなお、強気基調を保っていることも明らかだ。

(出所:Bloomberg)
換言すれば、米株高局面における米長期金利の低下は、リスクオフの視点をもって完全には説明しきれない。
まずテクニカル上の視点だが、米10物国債利回りが、2012年7月安値1.381%と2016年1月安値1.321%をもって「ダブルボトム」を形成し、2018年10月高値3.261%への反発をもたらした経緯に照らして考えると、目先の急落は、その切り返しへの反動と位置づけられ、また、すでに最終段階に入っているかと思われる。

(出所:Bloomberg)
換言すれば、前述の「ダブルボトム」を下回るような事態、目先は想定しにくく、RSIなどオシレーター系指標でみると、現時点ですでにかなりの「オーバーシュート」になっており、いつ底打ち、また反騰してもおかしくないだろう。
■ファンダメンタルズ的には米中対立激化が最大の材料だが…
ファンダメンタルズ上の視点として、やはり米中対立の激化が最も大きな材料であり、またFRB継続利下げの理由もそこにあるかと思われる。
ただし、繰り返し指摘してきように、そもそも米中対立は歴史的なテーマであり、中短期スパンをもってそれを相場に一気に織り込むには無理がある。
また中国に対して3000億ドル規模の追加関税を表明した米サイドは、関税カードをすべて使いきったことになり、米中貿易戦争自体が続くにしても、「関税の応酬は、これをもって一段落」といった思惑は逆に高まる。
■大幅な人民元安は、中国政府の自信の表れ?
米ドル/中国人民元の7元の大台乗せ(米ドル高・人民元安)をもって、通貨戦争という連想も多いが、現時点で人民元安が新たな段階に入ったと言えても、本格的な通貨戦争に突入したとは言い切れない。

(出所:Bloomberg)
なにしろ、中国政府は人民元安のカードを対米闘争の手段として持ち出しているが、そのカード自体は諸刃の剣であり、行きすぎた人民元安は対外債務の膨みや資金の海外逃避をもたらすから、人民元安を誘導、あるいは容認しつつ、しっかりしたコントロールを図るはずだ。7元の大台乗せを容認すること自体、むしろ人民元をコントロールできるという中国政府の自信がのぞく。
いずれにせよ、2015年のように、人民元ショックがあっても短期に終わり、昨日(8月8日)の米国株の大幅切り返しから考えても、そのショックがすでに修正されつつある、という可能性を無視できない。
■本当にリーマンショックの再来ならドル/円はすでに100円割れ
米ドル/円の話に戻るが、肝心のところ、ファンダメンタルズ上の材料がもたらした危機感は市場センチメントに反映され、一部市場参加者の解釈では、すでに2008年リーマンショックの再来と言わんばかりの状態において、値動きはそれに「比例」していないところが、最も大きなポイントだと思う。
つまるところ、マーケットはすべての予想や思惑を織り込んでいるから、リーマンショックの再来や本格的な通貨戦争に突入しているなら、米ドル/円は今の106円前後ではなく、とっくに100円の大台を切っているかと思う。
■米ドル/円は危機のたびに重要な安値を形成した
2015年高値から米ドル/円は大型トライアングルを形成してきた。そしていわゆる危機のたびに、重要な安値を形成した。
2016年6月の英国民投票によるEU(欧州連合)離脱決定、2018年3月の米中貿易戦争の勃発は、その典型であった。
さらに、2019年年初のフラッシュ・クラッシュもあって、米ドル/円は実に重要な安値を作りながら、その節目自体が右上がりをキープしており、前述の大型トライアングルを維持してきた。

(出所:Bloomberg)
英EU離脱にしても、米中対立にしても、足元改善されるどころか、むしろかなり悪化している状況において、ギリギリながら、米ドル/円がなお、同トライアングルを維持していることは見逃せない。
言ってみれば、相場は市場参加者の相違を反映しているから、リーマンショックの再来を皆さんが考えているなら、今のようなファンダメンタルズの悪化と「比例しない」値動きを維持できるわけはない。
■現時点の値動きは思惑をすべて織り込んだ結果である
さらに、相場は常に先取り、先走りする性質を持つから、現時点の皆さんの思惑を織り込まず、これから織り込んでいくこともない。現時点の値動きはそのすべてを織り込んだ結果と受け入れるからこそ、真の相場の本質を理解できるもの。
ゆえに、相場の行きすぎで、米ドル/円のさらなる下値打診の可能性を否定できないものの、円高トレンドへ復帰するのではなく、あくまで一時の行きすぎと見なし、オーバーな値動きがあっても前述の大型トライアングルの維持をなおメインシナリオとして位置付けたい。
さらに、主要クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)における2019年年初来安値更新は、そもそも米ドル高(ドルインデックス)がもたらした外貨安が主因だったことから考えて、足元すでに米ドル高(ドルインデックス)一服の兆しが出ており、クロス円における円高圧力の緩和が、米ドル/円の「底割れ」を回避させる一因になってもおかしくなかろう。このあたりの理由はまた次回にて詳説したい。
■予想ができないから「ショック」が発生する
最後に、目先リーマンショックの再来とか、米国株の暴落とかの予言が多いが、あまり神経質にならなくてもよいかと思う。
そもそもリーマンショックのような危機は、ウォール街の大手を含め、ほとんどの機関投資家も事前に予想できなかったから発生するもので、今のように、多くの一般人が警鐘を鳴らす状況で発生するわけはない。
こんなに多くの方がリーマン級の危機を予測できたら、もう町には超金持ちがいっぱいで、誰も働かなくなるだろう(笑)。
市況はいかに。













![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)
![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)







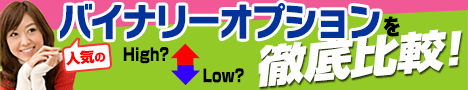
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)