■ユーロクロスが示唆する異変とは
米ドル/円は大幅下落、昨日(8月8日)一時、95円台の安値をつけ、前回のコラムの予想どおりの展開となった。
【参考記事】
●ドルインデックスは底打ちの可能性大だが、米ドル/円はなお下落余地が大きい!(2013年8月2日、陳満咲杜)
一方、ドルインデックスは、想定された200日線のサポートを割り込んだ形で、底打ちの兆しを見せず、予想が外れた。
ドルインデックスの下落は、8月2日(金)の米雇用統計が悪かったことを受け、ほぼ一直線に続いてきた。リンクしたように、ユーロ/米ドルの上昇もしかり。ここまでは理屈どおりの値動きで、何も特異なところなしと言いたいところだが、ユーロクロス(ユーロと米ドル以外の通貨との通貨ペア)に目を向ければ、ある「異変」に気づく。
まず、ユーロ/豪ドルは今週(8月5日~)からRSIの弱気ダイバージェンスを証左する形で一服し、反落してきた。ユーロ/米ドルの連騰にもかかわらず、ユーロ/豪ドルのブル(上昇)トレンドは、終焉の兆しを見せている。
(出所:米国FXCM)
ユーロ/豪ドルの反落をみれば、豪ドル/米ドルの底打ちや反騰も理解できる。RSIが示す強気ダイバージェンスはユーロ/豪ドルと正反対であり、豪ドルの底打ちは、遅ればせながらもユーロ/豪ドルの頭打ちと相俟って、いったん成功した公算が大きい。
(出所:米国FXCM)
次はユーロ/円だが、こちらは前回コラムでの指摘どおり、下落フラッグといったフォーメーションの形成途中と見られ、ユーロ安のトレンドが継続していく可能性が高い。
(出所:米国FXCM)
最後はユーロ/英ポンド。こちらもダブルトップをつけた形で騰勢一服、至って反落していく見通しが強まる。ユーロクロスは、総じて弱含みである。
(出所:米国FXCM)
強調しておきたいのは、ユーロクロス全般の弱含みは現在、ユーロ/米ドルの強気変動のなかで発生しており、先週(7月29日~)末から推進してきた米ドル全面安の流れでは、受け皿としてユーロ以外の外貨がより重要な役割を果たしていることは明らかだ。
したがって、ユーロが強いわけではなく、短期スパンにおける米ドル全面安の勢いが強かっただけ、という結論が得られる。
よって、ユーロプチバブルの崩壊は延期されたものの、現在最終段階に位置するといった判断は修正するどころか、むしろ強化されているとみる。もっともわかりやすいサインはユーロクロスの全面安であり、とりわけユーロ/豪ドルの頭打ちだと思う。
■ユーロ全面安の局面に備える必要あり
では、ユーロプチバブルの余地は、あとどれぐらい残っているのだろうか。ドルインデックスの週足を見てみれば、ある程度の感触を得られると思う。
(出所:米国FXCM)
ドルインデックスでは、2011年8月末安値から2012年1月安値を連結するサポートラインが、2011年5月安値を起点とした上昇波動のメインサポートラインとして意識される。
上のチャートが示すように、ドルインデックスは、すでに同ラインを打診しているから、同ラインの役割を再度確認できれば、そろそろ底打ちを図り、至って反騰してくるだろう。
米ドル全面安から米ドル全面高に転じれば、ユーロは受け皿としてもっとも売られやすいだろう。なぜなら、主要外貨のうち、ユーロがもっとも弱いことがユーロクロスの値動きで確認できたので、ユーロ安が先行しないとドルインデックスの反騰はあり得ないからだ。
まとめてみると、ユーロクロスの頭打ちがユーロ/米ドルの頭打ちより先行しており、ゆえに、ユーロ/米ドルの頭打ちもそれほど遠くないという見方である。この見方が正しければ、これからユーロ全面安の局面に備える必要がある。
米ドル/円とユーロ/円は、現在ほぼ連動した形でベアトレンドを展開しているが、前述の見方が正しければ、これから値動きにしても、変動スパンにしても、ユーロ/円の方がより大きくなるかもしれない。
言い換えれば、円高の主役は、現在の米ドル/円からユーロ/円などクロス円にシフトしていく可能性が高まっている。
■米ドル/円の下落はトライアングルの下限まで続く
米ドル/円の下落に関して、今でこそ円高方向にシフトした予想が多くなっているが、7月上旬から続いてきたもので、今さら驚くことではない。
いわゆるアベクロライン(チャートの緑のライン)を6月6日(木)にて割り込んだ後、7月8日(月)高値をもって同ラインの役割を確認しただけに、足元までの下落はごく自然な流れで、非常にわかりやすい市況だと思う。
【参考記事】
●カギは“アベクロライン”の平行線にあり!円安局面は外貨売り・円買いのチャンスか(2013年4月19日、陳満咲杜)
●米ドル/円の上昇は限界! 高値更新にはいったん下落が必要とみる理由とは?(2013年7月12日、陳満咲杜)
(出所:米国FXCM)
前述のアベクロラインの役割とは、要するに元のサポートラインは、いったん割り込むと今度はレジスタンスラインとして役割を展開してくるということである。
米ドル/円の値動きは、まさにこのような初心者向けのテクニカル教科書の模範のようになっているから、本来特筆すべきことではなかった。
円高トレンドの継続は、材料云々よりテクニカル上のサインがしっかりしていたので、軽視するのはあまりにももったいない。7月8日(月)高値を起点とした円高トレンドは、上のチャートで示すトライアングルの下限ラインを打診するまで続くと思われる。
もちろん、一直線に進まなかったり、同ラインを下回って、さらに下値余地を拓いたり、といったシナリオも同時に練っておくべきであろう(誤解されないように、言っておく)。
■ユーロ/円は年内118円台打診も?
ユーロ/円のチャートは、より深い調整の余地を示している。簡単に言うと、5月高値を「主尊」とする「三尊型※」の形成に注目、6月安値124.96円割れがあれば、2013年内に118円台の打診も視野に入れよう。
(※編集部注:「三尊型」はチャートのパターンの1つで、天井を示す典型的な形とされている。仏像が3体並んでいるように見えるために「三尊型」と呼ばれているが、人の頭と両肩に見立てて「ヘッド&ショルダー」と呼ばれることもある)
(出所:米国FXCM)
このような下値ターゲットの計算は、ユーロブチバブルの崩壊を暗示しているとも思われる。
■英ポンドと豪ドルはいずれ本来のトレンドへ復帰する
ところで、外貨のうち英ポンドと豪ドルは、それぞれファンダメンタルズ上の大きな変化が見られ、それを受けた形で短期スパンでは値幅を拡大している。
英ポンドでは、カーニー英中銀総裁によるFRB(米連邦準備制度理事会)のマネ(「フォワード・ガイダンス」の発表)、豪ドルでは、中国貿易数字の改善が挙げられる。
ただし、一般論としてこういった材料は長く影響力を保てないから、いずれ本来のトレンドへ復帰するとみる。この場合、より本質的なトレンドの決定要因は相場自身の要素である。
この意味では、豪ドル/米ドルの反騰は、英ポンド/米ドルより長く続くのではないかとみる。
なぜなら、豪ドルのネットショートポジションは、一時史上最高レベルまで積み上げられたから、英ポンドに比べ、解消するにはより長いスパンを要するかもしれないからだ。このあたりの話は、また次回。

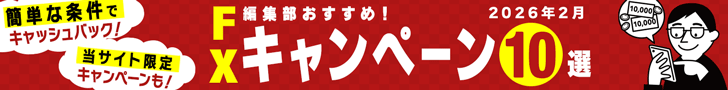

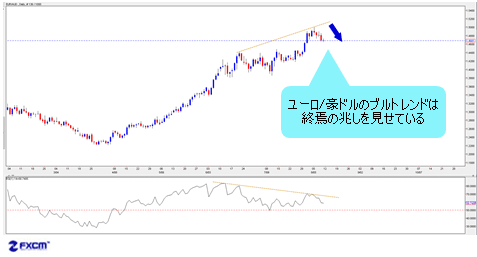



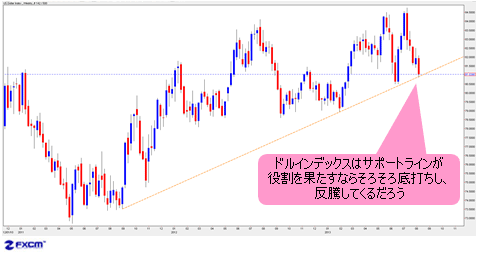
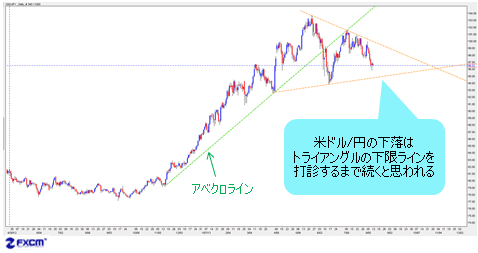
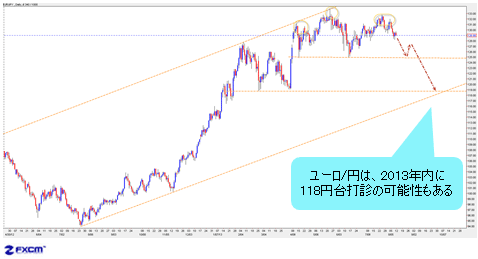











![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)

![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)







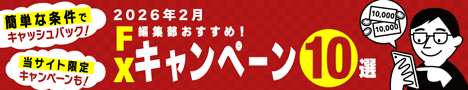
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)