週末にはピッツバーグでのシナゴーグ襲撃、メルケル首相が地方選で敗北、ブラジルの大統領選で極右候補が勝ちそうだ、などとマーケットの不安定さを増すようなニュースが多く出た。それでもアジア時間から欧州時間にかけてはどちらかというと極端なリスク回避の動きも見られず、比較的に平穏だったといえよう。
ニューヨーク序盤では米国株も大きく上がってきて、先週までの下げ分を取り返そうとする勢いにも見えた。しかしブルンバーグの報道によると、11月の米中会談で進展が見られなければ12月にも制裁の第4弾があると出たので、これが市場に不安を与えた。
米国株は激しくクラッシュし、今月の安値をも下回ってきた。しかし為替相場の反応は小さかった。ドル円もユーロドルもほとんど前日のレンジと同じようなものを形成するだけだった。
先週は米国株から欧州株も、そして日本株も大きく下げた。それもボラティリティの増大を伴ってだ。しかしだからといって何か新規の変わったことが起こったわけではない。経済ニュースや新聞で出てくるニュースは、1ヶ月前も年初も同じモノばかりである。
マーケットをリスクオフに傾かせているのは、中国との貿易戦争、EUや日本との自動車問題、アルゼンチンやトルコ、南アといった新興国のスプレッド拡大、トランプ政権の何が飛び出てくるかわからない不安定性、ハードなBREXIT、そしてイタリアの財政問題などだ。
これらはどれひとつとっても、前から言われてきたイシューであり、ずっと懸念されていたことだ。先週になって、いきなり湧き出してきたことではない。昨日は景気が良かったのに、明日は急激に景気が悪くなることはない。戦争でも勃発しない限りは、景気の変動は実になめらかなはずである。
そうした経済の底流に置かれているものを見つめる作業をファンダメンタルズ分析という。言うまでもなくファンダメンタルズはそう簡単には変わらない。今回の世界的な株価の激変においても、何もファンダメンタルズに変化は見られないのだ。
ファンダメンタルズ分析には経済指標が使われる。これは日頃、変わらないままでいるはずのファンダメンタルズの変化を見極めるためである。例えば金融当局による利上げなんかも、ファンダメンタルズの変更にあたる。それを確認するためにも経済指標のウオッチは欠かせない。
発表された時点ではマーケットで大きな反応が見られなくても、その指標が重要なモノであればあるほど、長く相場に効いてくるはずなのである。そしてそれが相場の流れを決定することになる。
具体的にファンダメンタルズをどのようにしてトレードに活かすことができるのか。もちろん経済指標の発表直後に相場の動いた方について行くというのも一手ではある。しかしこれでは短期的なトレンドフォローと変わらず、長いトレンドに追従することはできない。ファンダメンタルズに基づいたトレードというのは、毎回のポジショニングにおいて同じ方向のポジションしか作らないということに尽きる。
景気が悪くなると判断したならば、株価のショートでばかり攻めるのである。もちろんマーケットは毎日のことであるので、上がったり下がったりする。場合によっては損切りによって買い戻しも強いられるだろう。それでもファンダメンタルズの変化が見られない限りは、次に相場に入る場合もずっとショートでエントリーし続けるのである。
経済指標に見られるように外部環境がたいへん悪いので、景気が悪いはずだと判断したら、株やドル円などはショートで攻め続けることになる。もしも損だけが残ったならば、それは最初のファンダメンタルズの判断が間違っていたのだという解釈をするのである。
日本時間 15時00分
| 【2026年2月】ザイFX!読者がおすすめするFX会社トップ3を公開! | |||
| 【総合1位】 GMOクリック証券「FXネオ」 | |||
| GMOクリック証券「FXネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 24ペア |
|
【GMOクリック証券「FXネオ」のおすすめポイント】 機能性の高い取引ツールが、多くのトレーダーから支持されています。特に、スマホアプリの操作性が非常に優れており、スプレッドやスワップポイントなどのスペック面も申し分ないため、あらゆるスタイルのトレーダーにおすすめの口座です。取引環境の良さをFX口座選びで優先するなら、選択肢から外せないFX口座と言えます。 |
|||
|
【GMOクリック証券「FXネオ」の関連記事】 ■GMOクリック証券「FXネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼GMOクリック証券「FXネオ」▼ |
|||
| 【総合2位】 SBI FXトレード | |||
| SBI FXトレードの主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.18銭 | 0.3pips | 1通貨 | 34ペア |
|
【SBI FXトレードのおすすめポイント】 すべての通貨ペアを「1通貨」単位、一般的なFX口座の1/1000の規模から取引できるのが最大の特徴! これからFXを始める人、少額取引ができるFX口座を探している方は、絶対にチェックしておきたいFX会社です。スプレッドの狭さにも定評があり、1回の取引で1000万通貨まで注文が出せるので、取引量が増えて稼げるようになってからも長く使い続けられます。 |
|||
|
【SBI FXトレードの関連記事】 ■SBI FXトレードのメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼SBI FXトレード▼ |
|||
| 【総合3位】 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 | |||
| 外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の主なスペック | |||
| 米ドル/円 スプレッド | ユーロ/米ドル スプレッド | 最低取引単位 | 通貨ペア数 |
| 0.2銭原則固定 (9-27時・例外あり) |
0.3pips原則固定 (9-27時・例外あり) |
1000通貨 | 30ペア |
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のおすすめポイント】 業界最狭水準のスプレッドと豊富な情報で、多くのトレーダーに人気のFX口座です。FX取引が初めての初心者から、スキル向上を目指す中・上級者向けまで、各自のレベルにあわせて受講できる学習コンテンツも魅力です。比較チャートや相場の先行きを予測してくれる機能など、取引をサポートしてくれるツールも充実しています。 |
|||
|
【外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の関連記事】 ■外為どっとコム「外貨ネクストネオ」のメリット・デメリットを解説! スプレッド、スワップポイントなどの他社との比較、キャンペーン情報や口座開設までの時間、必要書類も紹介! |
|||
|
▼外為どっとコム「外貨ネクストネオ」▼ |
|||
| ※スプレッドはすべて例外あり。この表は2026年2月2日時点のデータをもとに作成しているため、最新の情報とは異なっている場合があります。最新の情報はザイFX!の「FX会社おすすめ比較」や、各FX会社の公式サイトなどで確認してください | |||
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!

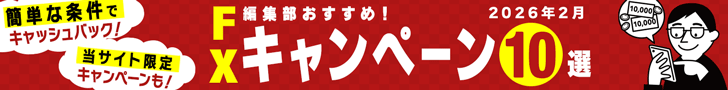
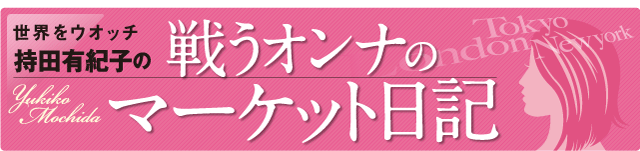
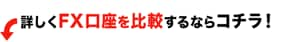
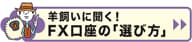



















![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](https://image.j-a-net.jp/1202907/1068901/)









株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)