【※関連記事はこちら!】
⇒経済指標の速報を、ほぼリアルタイムで知る方法! FX口座を開設すれば、誰でも無料で利用できるのが魅力! 「ロイター経済指標速報」を実際に使ってみた!
中央銀行の金融政策会合とは?
「中央銀行」とは、国の金融機構の中核となる公的な機関のこと。日本なら日銀(日本銀行)、ユーロ圏ならECB(欧州中央銀行)、英国ならBOE(イングランド銀行)、オーストラリアならRBA(豪準備銀行)が中央銀行です。
中央銀行の主な業務は自国の物価や金融システムの安定で、金融市場の状態を常に監視しつつ、自国の政策金利や主要金利の水準、当面の金融政策方針などを決めるための「金融政策会合」を定期的に開催します。
通常、各国の金融政策会合は一定のスケジュールに沿って定期的に開催されますが、リーマンショックやコロナショックのような、深刻な金融不安が生じたなどの理由で金融政策による早急な対応が必要と判断した場合は、臨時の会合を開催して政策金利の変更や、オペを通じた市場への資金供給などの金融政策を実施することもあります。
金利の水準や金融政策の運営方針は、為替レートだけでなく、金融市場全体にも大きな影響を及ぼすため、主要国の中央銀行の金融政策会合は非常に重要なイベントとして、FXトレーダーなら必ず結果を確認しておく必要があるといえます。
FOMC(米国の金融政策会合)
「FOMC」は通常、6週間に一度のペースで年に8回開催する、米国の金融政策を決める会合です。「Federal Open Market Committee」の略称で、日本語では「米連邦公開市場委員会」と称されます。
FOMCでは、「FF(フェデラル・ファンド)レートの誘導目標レンジ」、「今後の金融政策方針」、「先行きの景気動向や物価に関する判断」などが決定されます。
【※関連コンテンツはこちら!】
⇒米国の政策金利(FFレート)の推移と発表予定日をチェック!
米国には中央銀行にあたる単独の機関は存在せず、代わりに複数の組織体から構成されるFRS(連邦準備制度)という制度があります。FRSの構成機関の中に、中央銀行の役割を担うFRB(米連邦準備制度理事会)や、12の地区連銀(連邦準備銀行)などがあり、FRBが開催する金融政策会合がFOMCになります。
FRBには「物価の安定と雇用の最大化」という、2つの使命が課せられています。一般的にはデュアル・マンデートと呼ばれ、FOMCには物価と労働市場の状況を考慮しながらFFレートの誘導目標レンジを決定することが、FRSの根拠となる連邦準備法にも明記されています。
FOMCでは、FRBの議長・副議長を含めた7名、常任委員のNY連銀(ニューヨーク連邦準備銀行)総裁、NY連銀を除く11の地区連銀から1年交代の輪番制で選出された4名の地区連銀総裁、計12名のメンバーが議決権を行使して政策を決定します。FRB議長がFOMCの委員長を務め、FRBのポストに空席が生じているなどの理由でメンバーが12名に満たない場合も追加メンバーは補充されず、議決権のあるメンバーだけでおこなうのが通例です。
| ■2023年~2026年に議決権を有する地区連銀総裁 | |
| 2023年 | シカゴ・フィラデルフィア・ミネアポリス・ダラス |
| 2024年 | クリーブランド・リッチモンド・アトランタ・サンフランシスコ |
| 2025年 | シカゴ・ボストン・セントルイス・カンザスシティ |
| 2026年 | クリーブランド・フィラデルフィア・ダラス・ミネアポリス |
| ※常任メンバーのNY連銀を除く | |
※FRBの公式サイトの情報をもとに作成
・FOMCのスケジュールや注目点
通常時のFOMCでは、各地区連銀がそれぞれ管轄する地区の経済状況をまとめた「地区連銀経済報告書(ベージュブック)」、FRB調査統計局が提出する景気見通しをまとめた資料「グリーンブック」が議論の土台となり、メンバーによる単純多数決で政策を決定します。
毎回、火曜日と水曜日の2日間にわたって議論がおこなわれ、最終日の2日目にFOMCで決定した内容をまとめた声明文が公表されたあと、FRB議長による記者会見が実施されます。
米国がサマータイム(夏時間)中は、声明文の公表が日本時間翌午前3時、FRB議長の記者会見スタートが日本時間翌午前3時30分で、標準時間(冬時間)中は声明文の公表が日本時間翌午前4時、FRB議長の記者会見スタートが日本時間翌午前4時30分です。
また、一般的に3月・6月・9月・12月に開催されるFOMCでは、FOMCメンバーの金利見通しや経済予測を記したレポート「Economic Projections」が、声明文と同時に公表されます。ここには、オブザーバーとしてFOMCに参加している議決権のない7名の地区連銀総裁の意見も反映されています。
| ■FOMCのおもなスケジュール | |
| 会合名 | FOMC(Federal Open Market Committee) |
| 主催 | FRB(Federal Reserve Board) |
| 開催日 | 6週間に一度、年8回(通常1・3・5・6・7・9・11・12月) |
| 声明文の発表時刻 | 米サマータイム(夏時間)…日本時間翌午前3時 米標準時間(冬時間)…日本時間翌午前4時 |
| その他 | ・声明文発表の30分後からFRB議長の記者会見(毎回) ・2会合に1度(通常3・6・9・12月)、声明文と同時にEconomic Projectionsを公表 |
さらに、FOMCが終了した日から3週間後の水曜日には議事要旨(議事録)が公表されます。労働市場の環境、景気、物価などに関する見通し、金融政策の運営方針を決定するまでの、FOMCのより詳細な判断内容が盛り込まれているので、今後の金融政策の行方を見極めるための重要な材料となります。
・米国の政策金利「FFレート(FF金利)」とは?
「FFレート」は、米国の政策金利にあたる、米国の短期金利の代表的な指標です。
米国の民間銀行には、管轄する地区連銀へ預金残高の一定割合を預け入れることが義務づけられていて、預け入れる資金のことを「フェデラル・ファンド(Federal Funds)」、略してFFといいます。各行のFFは日々、預金残高にあわせて余剰や不足が生じるため、銀行同士が無担保で貸し借りをおこなうことができる銀行間取引市場の「FF市場」で調整されます。そこで適用される金利が「FFレート」です。FFには利子がつかないため、FFに余剰が生じた民間銀行はFFが不足している民間銀行に貸し出すことで、FFレート分の金利収益を得ることもできます。
FOMCは通常、0.25%のバンド幅となるFFレートの誘導目標レンジを決定し、公開市場操作(オペ)を通じてFFレートが誘導目標のレンジ内で推移するよう調整をおこないます。国債などの有価証券を購入して資金を供給する、保有している有価証券を売って資金を吸収するなどで、流通する資金の量をコントロールするのが一般的な手法です。
【※関連コンテンツはこちら!】
⇒米国の政策金利(FFレート)の推移と発表予定日をチェック!
なお、2008年11月までは、FFレートの誘導目標には一本値が採用されていましたが、2008年12月以降は上限と下限を設定し、そのレンジ内でFFレートを推移させる方針に変更されています。
民間銀行が預金残高の一定割合を預け入れるのは、金融不安などで金融機関の資金繰りが悪化した場合に備えるためのもので、米国以外の多くの国でも一般的に「準備預金」などと称し、中央銀行に預け入れるかたちの制度を導入しています。
日銀金融政策決定会合(日本の金融政策会合)
「日銀金融政策決定会合」は、日本の中央銀行である日銀(日本銀行)がおこなう政策委員会の会合のうち、当面の金融政策の運営方針などを決める会合です。6週間に一度、年8回のペースで開催されますが、政策委員会の議長である日銀総裁が必要と認めた場合や、政策委員会の3分の1以上のメンバーが議長に招集を求めた場合は、臨時で開催されることもあります。
通常の日銀金融政策決定会合は、各会合とも2日間の日程でおこなわれ、2日目の会合終了後に決定事項の公表と、日本時間午後3時30分から日銀総裁の記者会見が実施されます。決定事項は会合終了後に直ちに公表されることになっていて、他の主要国のように発表時刻が決まっていないという特徴があります。
【※関連コンテンツはこちら!】
⇒日本の政策金利の推移と発表予定日をチェック!
また、通常1月・4月・7月・10月に開催される会合では、政策委員による実質GDPと消費者物価指数の大勢見通しや、基本的見解などが盛り込まれた「経済・物価情勢の展望(展望レポート)」が、会合の決定事項とあわせて公表されます(背景説明を含む全文は翌営業日)。特に、消費者物価指数の先行きの見通しについては、日銀の金融政策方針の変更時期などを予測するうえで注目されます。
| ■日銀金融政策決定会合のおもなスケジュール | |
| 会合名 | 日銀金融政策決定会合 |
| 主催 | 日銀(日本銀行) |
| 開催日 | 6週間に一度、年8回(通常1・3・4・6・7・9・10・12月) |
| 声明文の発表時刻 | 会合終了後、直ちに |
| その他 | ・日本時間午後3時30分から日銀総裁の記者会見(毎回) ・2会合に1度(通常1・4・7・10月)、「経済・物価情勢の展望(展望レポート)」を公表 |
そのほか、原則として各会合の6営業日後には、会合における「主な意見」が公表されるほか、会合のより詳細な内容が記された議事要旨は、次回の会合で承認を受け、承認から3営業日後に公表される決まりとなっています。
ECB理事会(ECB政策理事会・ユーロ圏の金融政策会合)
「ECB理事会」は、ユーロ圏の統一的な金融政策を担う中央銀行のECB(欧州中央銀行)が定期的に開催する会合です。そのうち、当面の金融政策の運営方針などを決める「政策理事会」と呼ばれる会合は、ECBの役員会メンバー6名、ユーロ圏の中央銀行総裁19名の計25名で構成され、通常はおおむね6週間に一度、年8回のペースで実施されます。
政策理事会は毎回、木曜日に開かれるのが通例で、会合終了後に金融政策方針の発表と、ECB総裁の記者会見がおこなわれます。欧州がサマータイム(夏時間)中は、金融政策方針の発表が日本時間翌午後8時45分、ECB総裁の記者会見スタートが日本時間午後9時30分で、標準時間(冬時間)中は声明文の公表が日本時間午後9時45分、ECB総裁の記者会見スタートが日本時間午後10時30分です。
政策理事会では、政策金利にあたる「主要リファイナンス・オペ金利」、金融機関がオーバーナイトでECBに資金を預け入れるときに適用される「預金ファシリティ金利」、金融機関がオーバーナイトでECBから資金を借り入れるときに適用される「限界貸付ファシリティ金利」の主要金利のほか、資産購入プログラム(APP)などの資金供給支援に関する方針も協議され、参加者の多数決によって政策が決定します。
【※関連コンテンツはこちら!】
⇒ユーロ圏の政策金利の推移と発表予定日をチェック!
また、2会合に1回のペースで、ユーロ圏の成長率やインフレ率の予想を示した「スタッフ予想」が金融政策方針の発表を同時に公表され、各会合の4週間後には議事要旨も公表されます。
| ■ECB理事会のおもなスケジュール | |
| 会合名 | ECB理事会(ECB Monetary policy decisions) |
| 主催 | ECB(European Central Bank) |
| 開催日 | おおむね6週間に一度、年8回 |
| 声明文の発表時刻 | 欧州サマータイム(夏時間)…日本時間午後8時45分 欧州標準時間(冬時間)…日本時間午後9時45分 |
| その他 | ・声明文発表の45分後からECB総裁の記者会見(毎回) ・2会合に1度(通常3・6・9・12月)、声明文と同時に「スタッフ予想」を公表 |
※当面の金融政策を決定する「政策理事会」に該当する会合を記載
そのほか、英国のBOE(イングランド銀行)が開催する「英MPC」、オーストラリアのRBAが開催する「RBA理事会」など、主要国の金融政策を決める会合は、その国の通貨の値動きに影響を与えるイベントになる可能性があるため、該当する通貨が絡んだペアをFXで取引しているときは、特に注意しておく必要があります。
【※関連記事はこちら!】
⇒経済指標の速報を、ほぼリアルタイムで知る方法! FX口座を開設すれば、誰でも無料で利用できるのが魅力! 「ロイター経済指標速報」を実際に使ってみた!
| 【2026年2月】ザイFX!読者に人気のFX口座はココ!(ランキング・トップ3) | |
|---|---|
| 【総合1位】GMOクリック証券「FXネオ」 ⇒詳細ページ | |
|
|
|
 |
|
| 【総合2位】SBI FXトレード ⇒詳細ページ | |
|
|
|
 |
|
| 【総合3位】外為どっとコム「外貨ネクストネオ」 ⇒詳細ページ | |
|
|
|
 |
|
【※4位~10位も含む、各口座のおすすめポイントやキャンペーン情報はこちら!】
⇒FXおすすめ口座人気ランキング! ザイFX!読者が選んだ 人気No.1のFX口座はここだ! FX初心者も必見! おすすめのFX口座を詳しく比較

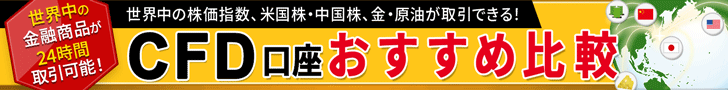
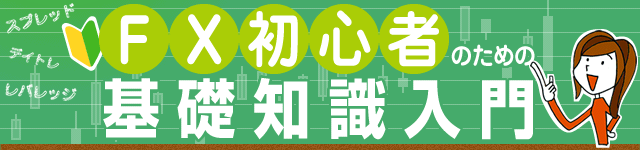
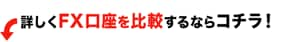
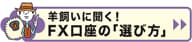











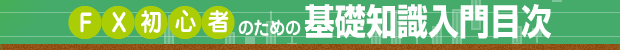










![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)







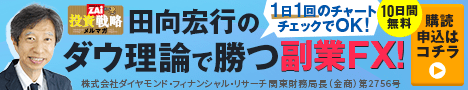
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)